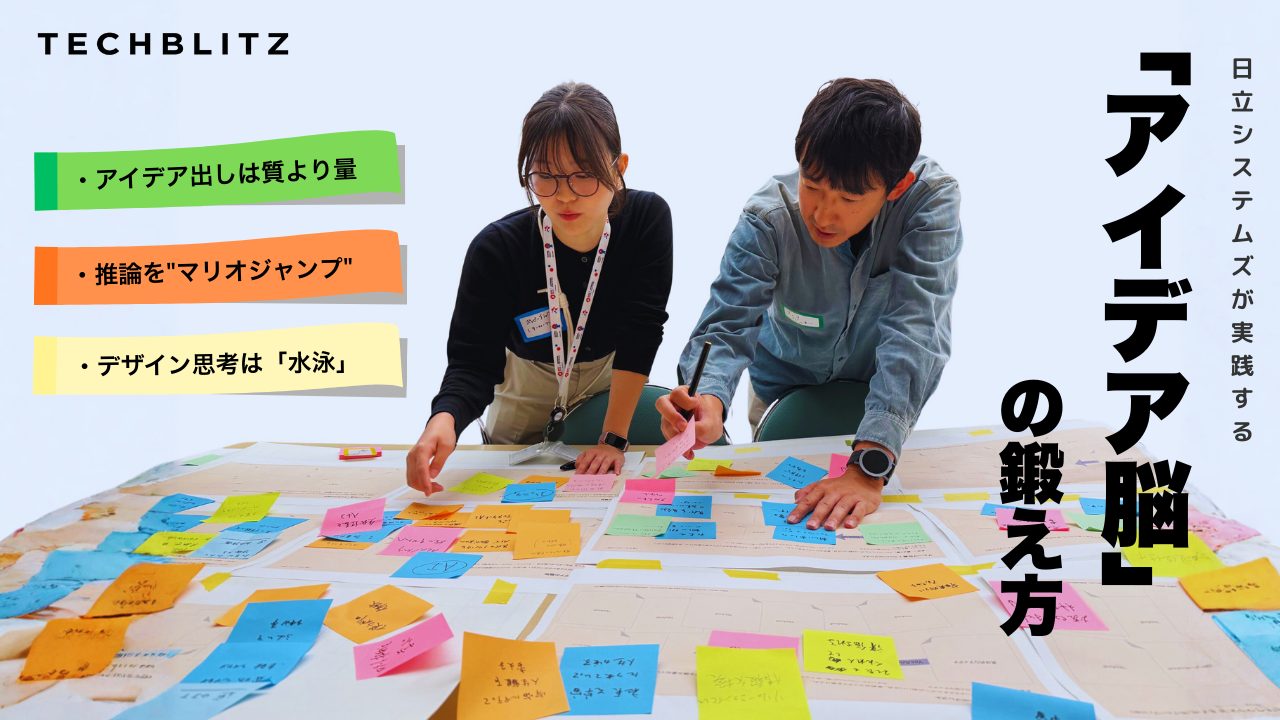目次
・オープンイノベーションの実現はキャッチャー次第
・「スタートアップと連携する目的」をぶらすな
・「ピッチャーからキャッチャーへ」の人材サイクルを回す
・社員が海外で起業?「スタートアップ創出制度」とは
オープンイノベーションの実現はキャッチャー次第
―御社では2007年からシリコンバレーでの活動をスタートさせています。スタートアップと組む理由を教えてください。
日立ソリューションズがスタートアップと組む理由は、以前から変わっていません。お客様から提示された課題に応えるだけのSIの時代が終わり、顧客ニーズの多様化、プロダクトサイクルの短期化、技術革新の加速、ビジネスモデルの多様化が進む中で、「自社開発のみにこだわっていては未来がない」という危機感を覚え、ビジネスモデルやマインドセットの変革が必要だと実感したからです。

―具体的な取り組みについて、まずは海外側である「ピッチャー」の役割について教えてください。
シリコンバレーでスタートアップを発掘し、彼らと交渉するほか、現地の最新トレンド情報などを日本へ発信することが、ピッチャーの役割です。
ピッチャーの役割として重要なのは「自社を知り、スタートアップやVCと的確に共有する」ことです。現地では日立グループや当社について、誰も、何も知りません。というのは言い過ぎかもしれませんがそれぐらいのつもりで、その上で「自分たちがどんなビジネスを展開しており、どんな強みがあるのか」を端的に説明すること。そして、自社の販売チャネルや技術リソースをどれだけスタートアップに提供でき、スケール化にどう貢献できるかなど、「どのようなビジネスができるか」を伝えることが大事です。
スタートアップへのリスペクトも忘れてはいけません。「われわれは日本の大企業です」という態度では、相手にしてはもらえません。シリコンバレーでは、われわれが選んでもらう立場なのです。貴重な時間を使って会ってくれていることを感謝し、先陣を切って自社の関心・興味を伝え、彼らのビジョン、ペインポイント、解決策を理解し、共感することも非常に大事です。
さまざまなスタートアップに話を聞くと、「日本企業は『知りたい』『教えて』が強すぎて、なかなか自分たちの情報を提供しない」と言われます。アーリーステージ企業に対しても、「サポートは?」「品質基準は?」といった大企業ならではの定型的な質問をぶつけてくることも多いと。ピッチャーはそうした質問を精査し、場合によってはフィルタリングし、真にぶつけるべき的確な質問を伝えることも重要だと考えます。「ギブ・アンド・テイク」の精神を持ち、まずは「こんなニーズがある」「こんなビジネスができないか」など自社の情報・ニーズの「ギブ」を続ける必要があると考えています。

image: 日立ソリューションズ
―続いて、日本側である「キャッチャー」の役割について教えてください。
ピッチャー役が投げた「球」を日本で受け入れるのがキャッチャー役であり、オープンイノベーションの実現はキャッチャー次第とも言えます。当社では、東京の戦略アライアンス部と各事業部の企画部門がキャッチャー役となります。ちなみに私は、シリコンバレーでピッチャー役を、帰任した現在は事業部の企画部門でキャッチャー役を担っています。
キャッチャー役は「日本とアメリカの通訳」であることが必要です。自社・部門の課題・ニーズを把握し、適切な言葉でピッチャーに伝えると同時に、ピッチャーからの情報を適切な言葉で社内・部門に伝えることも求められます。そのためには、「社内で少し浮いている存在」ぐらいがいいのかなと。日本にいながらもシリコンバレーのマインド、スピード、ビジネスの動かし方、自社の立場などを理解し、社内のロジックに迎合しすぎない姿勢を保ち、上層部へも忖度せずに状況説明ができなければいけませんから。

image: 日立ソリューションズ
「スタートアップと連携する目的」をぶらすな
―ピッチャーとキャッチャーの体制をうまく回していくために、工夫はされていますか?
当社では事業戦略ポートフォリオマップを作成しています。そこでは、①自社開発では技術進化のスピードに追いつけない、該当技術が社内にないといった「足りないピース」を埋める、②リスクを低減して新たな領域にチャレンジする、というスタートアップ活用目的の基本方針が示されています。なお、「足りないピース」「新たな領域」については近視眼的にならないよう、事業部側とシリコンバレー側の意見をぶつけ合って落とし込んでいます。この基本方針がぶれると、社内で「苦労してスタートアップと連携する必要があるか?」という意識の乖離が生まれかねません。まずは、こうした基本方針を共通認識として保持することが必要です。

image: 日立ソリューションズ
その上で、「小さな成功(実績)」を目指していきます。興味を持ってくれそうな事業部など社内でターゲットを定め、少しずつ活動を進めていくのです。当社の場合は、まずセキュリティやクラウド分野など、新たな技術を欲する事業部から巻き込んでいきました。同時に、社内へトレンド情報を提供したり、現地を体感してもらったりなどして少しずつファンを増やしながら、協業検討がスムーズに進む手立てを探っていきました。経営陣がそもそも「既存事業の業績が良くても、将来への新たな可能性を探るべき」という認識を持っていたところにシリコンバレーで最先端を体感したことで、スピードが高まったと感じています。
こうした地道な努力を積み重ね、10年以上をかけて現在のような全社・全事業部対象の体制が出来上がりましたね。
―「なかなかオープンイノベーションへの意識が高まらない」「現業の力が強すぎる」というケースも多いと思います。
いきなり全社一丸となるのは難しいでしょう。当社でも関心を示さない部門はありましたが、成功事例が増えてくると、経営陣から「なぜ活用しないのか?」といった、ある種のトップダウンのような動きも起こるようになりました。とはいえ、そういった部門に対してもいきなりスタートアップの紹介をするのではなく、まずは最新トレンドや事業に関連する情報の提供から始め、徐々に価値を感じてもらえるような流れをつくっていきました。活動自体が「普通のこと」になるにはどうしても時間がかかり、特効薬のようなものはないと思います。
また、経営陣の理解が得られると、法務や調達など間接部門も動き出します。こうした部門を含めた一体化体制ができたことで、スタートアップ界隈での評価も向上したと感じています。
―活動が成熟していくにつれ、KPIは変わっていきましたか?
KPI自体はあまり細かく定めていないのですが、スタートアップとの事業化成功件数は変わらず立てています。それ以外は主眼を置く場所が少しずつ変わってきています。15年ほど前の活動スタート時はまず「スタートアップの発掘・紹介件数」、その後活動が進むにつれて「事業化検討着手件数」ならびにその着手率(ヒット率)を重視していましたが、最近では「スタートアップやトレンドなどの情報提供数」「カンファレンス調査報告件数」などに主眼を置いています。紹介するスタートアップも直接事業化検討に繋がるものだけではなく、将来的なトレンドになりそうなものをいち早く紹介したりと、事業化成功だけではなく、社内啓発やそのプロセスも重視するかたちにシフトしていますね。
「ピッチャーからキャッチャーへ」の人材サイクルを回す
―スタートアップとの協業活動を継続させていくために、人材育成はどのように行っていますか?
主に3つのプログラムを用意し、「シリコンバレーにピッチャー人材を送り続け、帰任者にキャッチャー対応してもらう」という人材のサイクルを回しています。
①キャッチャー体験型
まず「キャッチャー体験型」は日本で数カ月間、キャッチャー業務を担い、その後シリコンバレーでピッチャー業務を、帰任後は再びキャッチャー役として事業部に戻るシステムです。私もこのパターンに当てはまります。
②研修型
「研修型」では、若手の未経験者にカンファレンスや展示会へ参加してもらうことで活動への興味喚起を促すという、裾野を広げる活動も始めています。
③リエゾン・BAP体験型
「リエゾン・BAP体験型」という、1年間の業務研修やDNX Venturesが提供するBAPビジネスアクセラレーションプログラムなどを通し、シリコンバレーでの事業開発を体験できるプログラムもあります。

image: 日立ソリューションズ
確かにスタートアップ活動が進んでアライアンス品が増え、当社のビジネスは拡大しました。その一方で、「自社のコアコンピタンスが薄れてきている」という課題も生じています。以前は高額なソフトウェアも売れていましたが、近年は薄利のSaaS型が増えたほか、ボーダレス化やグローバル化、国内市場の低成長などの要因が重なり、グローバルで売れないと事業性が難しくなっているのです。
当社は過去にも北米を中心とした海外展開を行ってきましたが、市場ニーズへのマッチングやスケール化などにつまずき、大きな成果にはつながりませんでした。
社員が海外で起業?「スタートアップ創出制度」とは
そこで昨年、北米市場をターゲットにした社内制度「スタートアップ創出制度」をスタートさせました。シリコンバレーの起業ノウハウを活用し、現地で新規海外事業の創生と事業をスケールさせるという内容です。具体的な進め方については、以下の通りです。
- STEP 1:1チーム2人の候補者を募り、社内選考会を実施
- STEP 2:審査を突破したチームがシリコンバレーに1年間赴任し、DNX Venturesの起業トレーニングを受講
- STEP 3:同時に北米マーケットでの仮説検証を進める
- STEP 4:投資家向けへのピッチで独立の判断を行う
- STEP 5:当社とDNX Venturesで立ち上げたファンドから活動資金を出資し、プレシードとして会社設立
- STEP 6:外部のベンチャーキャピタルからの出資を獲得できれば、当社を退社し、独立して会社運営へ
- STEP 7:スケール化した場合は先端商材として国内展開を実施

image: 日立ソリューションズ
この過程でうまくいかなかったとしても、会社に戻って再び活躍できることが、本制度の大きな特徴です。スタートから1年が経ちましたが、STEP 05の「会社設立」ステージに移った事例も生まれました。「独立してさらに成長し、我々が使える商材を育ててほしい」という思いはあるものの、スタートアップ業界全体でもそこまでに至る企業は1割ほどですし、かなり時間もかかるものです。結果を急ぐのではなく、現在はこの活動を継続させることに重きを置いている状況ですね。本制度によってグローバルニーズに対応できる新規事業の創生だけでなく、「シリコンバレー流の事業開発やスケール方法の取得」「起業マインドを持つ人材育成」「チャレンジできる企業風土の形成」といった効果も期待しています。
―実際に1年間プログラムを回されて、どのように総括されますか?
シリコンバレーの人材やコミュニティをうまく活用し、日本よりも圧倒的なスピード感で、さまざまなことを検証しながら、さらにピボットしたり市場に合わせたりしながら、プロダクトを進化させていけていると感じています。大企業とは違う動き方で、英語で、スピーディにこれらを実行するのはかなり大変なことです。もちろん、カタチがないものを1年で具現化させていくという難易度の高さもしかり。そうした成果や課題が、ようやく見えてきたところでしょうか。同時に、「自社開発・自社技術ファーストだった日立ソリューションズでも、オープンイノベーションを進めることができた」という思いもあります。
こうした取り組みをさらに骨太にしながら継続させ、「グローバルで戦える企業をつくりあげる」ことが、我々の究極の目的です。