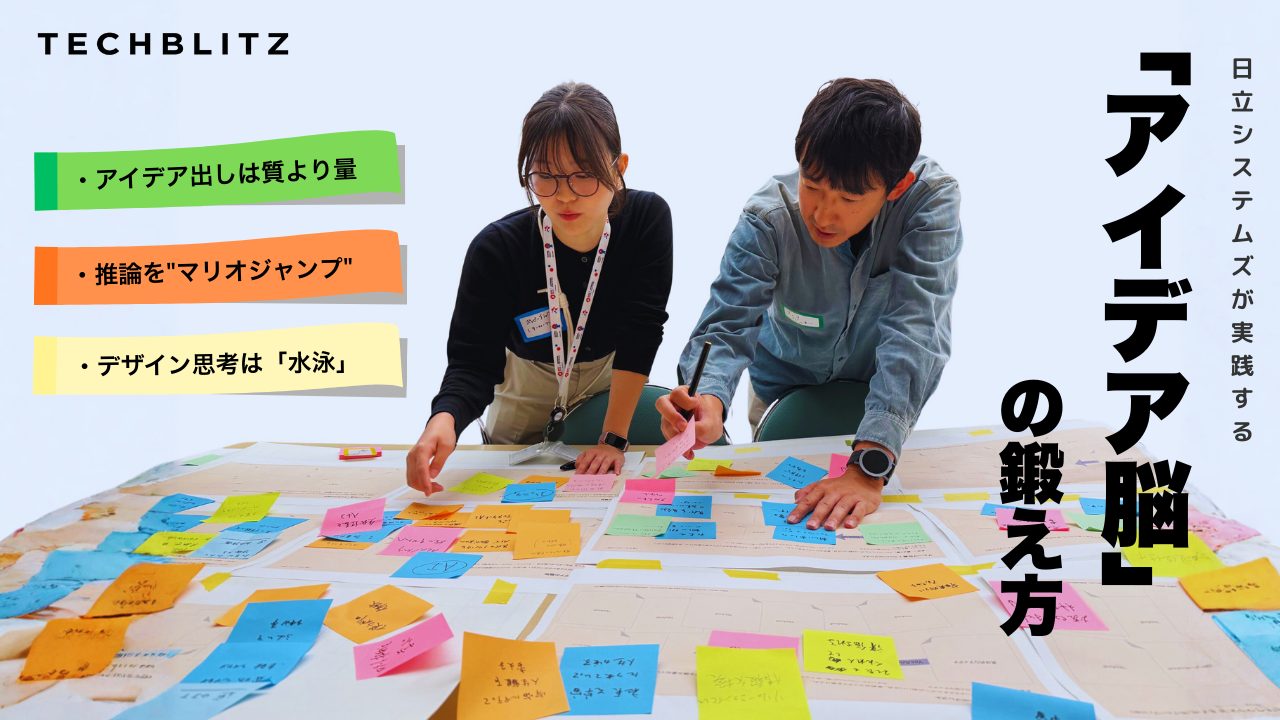*'After all, Silicon Valley isn’t just a place — it’s a state of mind' Marc Andreessen, Andreessen Horowitz:「What It Will Take to Create the Next Great Silicon Valleys, Plural」
目次
・シリコンバレー研修を立ち上げたワケ
・5日間集中型、シリコンバレー研修の内容とは
・シリコンバレーで体感、“本場”のデザイン思考
・参加者の変化①:「Yes, and」を社内で実践
・参加者の変化②:「完璧よりスピード感」
・「変われる組織」への進化を目指して
シリコンバレー研修を立ち上げたワケ
―シリコンバレーでの社員向け研修プログラムを始めた背景を教えてください。
市川:私は社内転職をきっかけに2019年にシリコンバレーに赴任し、現地でTECHBLITZ主催の「Silicon Valley - New Japan Summit」というイベントに参加しました。その中の対談で、シリコンバレーを人材育成の場として活用する日本企業の取り組みを知ったのが、研修プログラムを立ち上げたきっかけです。
ちなみに、私はもともとセキュリティエンジニアとして20年以上のキャリアを積んできました。セキュリティ分野というのは「いかにリスクをゼロに近づけるか」が本質で、「守る」ことが役割です。一方、イノベーションは新たな価値を生み出す、「創る」取り組みです。両者は異なる側面を持ちますが、守るだけではなく創る側に回りたいと考え、イノベーション専門部署への異動を希望し、現在のポジションにいます。
.jpg)
シリコンバレー研修発足の背景などについて語る市川さん(TECHBLITZ編集部撮影)
―その対談のどういった内容に影響を受けたのですか?
市川:対談は「シリコンバレーを活用した人材育成」と題した、三菱商事さん・スズキさん・鹿島建設さんの3社によるものでした。その対談を通じて、シリコンバレーをスタートアップや新技術の「探索の場」としてだけでなく、「人材育成の場」と捉えた取り組みがあることを知ったのです。
特に印象的だったのは、「腐った土からは何も生まれない」という、登壇者の一人の発言です。組織の根本となる人材のマインドセットが変わらなければ、どんなに優れた戦略や技術があっても意味がない、という趣旨ですね。この言葉は刺激的でした。
また、皆さんが揃って「(会社が)変わらなくてはいけない」という危機感を持っていたことにも突き動かされました。これほどの大企業が揃って危機感を持ち、将来を見据えた打ち手を講じているのだなと。

―イベントをきっかけにして、具体的にどのような行動を起こされましたか?
市川:イベント後に各社を直接訪問し、「全部教えてください」と頭を下げました(笑)。皆さん本当に快く、何から何まで教えてくれました。当社のような異業種、あるいはライバルの同業に対してですら、知見をオープンに共有して、協力しながらイノベーションを生み出す。この姿勢こそが、シリコンバレーの文化として根付いている「オープンイノベーション」なのだと強く実感しましたね。
こうした経緯から、三菱商事さんが実際に行っている内容をモデルにさせていただき、当社の研修プログラムを立ち上げた次第です。

5日間集中型、シリコンバレー研修の内容とは
―御社のシリコンバレー研修プログラム「イノベーション・ブートキャンプ」について教えてください。
市川:イノベーション・ブートキャンプは若手社員らがシリコンバレーを実際に訪れて行う、5日間のプログラムです。複数の現地パートナーと連携し、実践的なアプローチを体験する中でシリコンバレー流のマインドセットを集中的に浴びる、かなり中身の濃い内容となっています。
2021年から始動し、最初は事業部長やそれに準ずる役職層を対象に行いました。新型コロナの流行期だったのでオンラインでの実施でしたが、部長クラスのスケジュールをまとめて確保するのは相当難しいので、むしろ参加してもらいやすい側面もありましたね。2024年と2025年は若手社員へと参加者の層を移行させ、現地に足を運ぶ本来の姿に戻っています。

シリコンバレー現地で開催された研修の一幕(NECソリューションイノベータ提供)
―具体的に、どのような内容で構成されているのですか?
2024年を例に挙げると、プログラム初日は、シリコンバレー特有のスピード感やイノベーションの考え方を学ぶワークショップからスタートします。2日目以降は、現地の起業家からアントレプレナーシップを学ぶセッションや、スタンフォード大学の教育機関「d.school(ディー・スクール)」の講師による「デザイン思考(Design Thinking)」、望ましい未来像から逆算して現在の行動を考える「未来思考(Future Thinking)」へと続きます。
初日のワークショップで特に強調されるのは「ユーザーファースト」の重要性です。当社の社員は顧客企業のさらに先にいる「お客様」、つまりエンドユーザーと直接接する機会が少ないため、本当の意味でのユーザー視点が抜けがちになります。表面的な仕様や要望だけでなく、背景にある本質的なニーズを探る姿勢の重要性に気づかされるわけですね。
2日目からのデザイン思考では、「街に出て人に話を聞く」フィールドワークをおこないます。ほとんどの参加者たちにとっては初めての経験であり、文化的な違いから最初は戸惑いもあるようですが、対話を重ねることで多くの気付きを得ています。

2024年に実施されたBootCamp研修プログラムの5日間の日程(TECHBLITZ編集部作成)
シリコンバレーで体感、“本場”のデザイン思考
―デザイン思考は2日間にわたるセッションで、研修プログラムの大きなハイライトの1つですね。参加者はここで、どのような学びを得るのでしょう?
市川:デザイン思考のセッションを通じて伝えられるのは、仮説を立て、ユーザーの声を拾い、スピード感を持って何度も試すことの大切さです。例えば、4,000のアイデアの中から125のトライアルをして、最終的に残るのはほんの2〜3個というメソッドも紹介されます。「数を打つこと」と「現場の声を聞くこと」、この2つがイノベーションの起点になるというメッセージが、参加者に強く刻まれると思います。
「数多くのアイデアを出す」ことが求められるので、とにかく質よりも量を重視する姿勢が強調されていました。日本では、出てきたアイデアに対して「それってどうなの?」「現実的じゃないよね」といった評価を加えがちですが、ここでは「良いね、それならこういうのは?(Yes, and)」と、次々にアイデアをつなげていく訓練が行われます。
そうすることで、突拍子もないものの中から貴重なアイデアが生まれたりします。平凡から遠ければ遠いほどイノベーションが生まれる、そういうエネルギーを秘めています。日常業務ではなかなかできませんが、「飛躍させる」練習、デザイン思考で言うと「発散」に当たるフェーズですね。
―デザイン思考には「発散」に続く、「収束」のフェーズもありますよね。
市川:はい、こうして出されたアイデアを機械的に絞り込む「収束」フェーズも印象的です。付箋に書いたアイデアにシールで投票して、上位のものだけを残し、他は潔く捨てるプロセスを経験します。
私たちは、この「捨てる」という行為が非常に苦手です。日本では人やプロジェクトに対する配慮から、なかなか思い切った判断ができない現実もあります。しかし、スピード感を持って「アイデアを出す、捨てる」を繰り返すことこそが新しいものを生み出す。捨てられた小さなアイデアを追い続けるのではなく、またプロセスを回せばいいじゃないかという考え方ですね。

参加者が付箋に書いたアイデアの数々も「潔く」ごみ箱に捨てられる(NECソリューションイノベータ提供)
―頭では分かっていても、実際にやってみると難しそうです。特に、「捨てる」という判断には勇気が必要ですね。
市川:まさにそうです。デザイン思考というと「発想法」のイメージが先行しがちですが、実は一番大事なのは「ユーザーの話を丁寧に聞く力」と「アイデアに執着しない勇気」だと実感しました。日本のビジネス現場に持ち帰るにはアレンジが必要だと思いますが、この姿勢の部分は、業界を問わず取り入れる価値があると強く感じます。
―デザイン思考も含めて、これらの研修コンテンツを現地で体験することには、どんな狙いがあるのでしょうか?
市川:よく誤解されるのですが、デザイン思考を含む一連のプログラムは「スキル研修」ではありません。「短期間で何かができるようになる」ための研修ではなく、「マインドを変えるためのきっかけ」を作る場なのです。そのためにあえて、シリコンバレー現地での体験を重視しています。
日本でも似たようなプログラムを提供する企業はあります。でも、シリコンバレーでの経験を通じて分かったのは「環境が人の意識を変える」ということです。単なる研修コンテンツではなく、シリコンバレーで中核的な役割を果たす地域のパロアルトをはじめとした「その土地の空気」を感じ、異なる価値観に触れることこそが重要だと考えています。それによって、自分の視野がいかに狭かったかを実感し、多様な考え方が共存することの強さを学べるからです。
参加者の変化①:「Yes, and」を社内で実践
―ここで、2024年の研修に参加した亀井悦子さん・尾地肇さんのお二人に、その後の変化や実践についてお話を伺います。まず亀井さんから、研修後はご自身の中でどのような変化がありましたか?
亀井:実際に私も参加してみて、まさにマインドの部分が変わったと感じました。もちろんスキルの部分にも変化はありましたが、それ以上に、「ものの見方」とか「考え方」がガラッと変わった感覚がありました。
ただ、私だけマインドが変わっても意味がないと思い、上司にお願いして週1回の定例会議の中で「Yes, and」のワークショップを取り入れてもらいました。
.jpg)
ラインスタフ統括部DMX企画グループ主任の亀井悦子さん(TECHBLITZ編集部撮影)
―「Yes, and」というのは、先ほど市川さんがおっしゃっていた、アイデアを否定せずに“乗っかる”コミュニケーション手法ですよね。
亀井:はい。10人くらいでも15分もあればできます。誰かがテーマを出して、それに対して他のメンバーが「Yes, and」でアイデアを重ねていくという流れです。最初は正直、みんな恥ずかしそうでした。でも、そこをあえて毎週続けることで、少しずつ雰囲気が柔らかくなっていって。気付けばもう1年くらい、継続しています。
特に印象的だったのが、「(NECソリューションイノベータの本社がある)新木場駅前をもっと良くするには?」というテーマで取り組んだワークでした。新木場駅は、舞浜やお台場に近く、京葉線(JR)、りんかい線(東京臨海高速鉄道)、有楽町線(東京メトロ)も通っているターミナル駅です。でも、実際に降りる人は少なく、利用者はほぼ会社員ばかり。そんな駅前に何があればいいかという発想から始まり、最終的には「地上にスペースがないなら地下を開発しよう」という、「新木場地下開発計画」が出てきました(笑)。現実的には地盤の問題で難しいかもしれませんが、それでも「そんなのアリ?」っていうくらい大胆なアイデアが出てきたのです。
やっぱり、「現実的かどうか」ばかりを考えると平凡な案しか出てこない。でも、「Yes, and」のマインドで自由に発想するようになると、突拍子もないけどワクワクするようなアイデアも生まれてくる。実際、その新木場のワークはメンバーからも上期の総評で「一番面白かった」と好評でした。
今では通常の会議でも「Yes, andでいきましょう」という言葉が自然と出てくるようになり、少しずつですが、チームの文化として根付いてきた実感があります。あの時の研修がきっかけで、確実にチームの空気が変わりました。
参加者の変化②:「完璧よりスピード感」
―尾地さんはいかがですか?
尾地:大きく意識が変わったのは、「まず作ってみる」という姿勢ですね。
私は今、お客様の要望をベースにする業務ではなく、どちらかというと研究開発寄りの仕事をしています。だからこそ、「こういうものがあったら良いのではないか」と自分たちで考えたものを、まず形にしてみて、それを起点に議論をしていく。そんなプロセスが大事になります。
研修をきっかけに、その「形にする」までのスピードに対する意識がかなり変わったと思います。例えば以前だったら、何日もかけてちゃんと資料を作ってから出すという流れでしたが、今は「とりあえず30分でラフでもいいから作ってみる」というスタンスになってきました。
職人気質な会社なので、どうしても「ちゃんとしたものを作らなきゃ」「完成度が低いと恥ずかしい」という空気は強いところがあります。でも、そうやってモタモタしているうちに、世の中はどんどん変わっていく。今「いい」と思っていることも、明日には求められないかもしれない。だったら、スピード重視で動いて「まず出してみよう」というマインドに切り替えられたのは大きいです。そういう意識を自分から日常業務に持ち込んで、少しずつ実践しているところです。
.jpg)
「アイデアなどを提案する際のスピード感に対する意識が変わった」と話すPB事業開発室の尾地肇さん(同)
「変われる組織」への進化を目指して
―では、最後に市川さんに伺います。この研修を足掛かりに、組織全体にどんな変化が生まれることを期待していますか?
市川:まずは、この研修を一度経験した社員が増えていくことで、組織全体のマインドが変わっていくことを期待しています。
人材育成の話になると、どうしても「できないことをできるようにする」「スキルを身につけさせる」といった目に見える成果を重視しがちです。目に見える成果が一番理解されやすいので、どうしても「マインドにお金をかける意味」を問われてしまうこともあると思います。
ありがたいことに、当社の経営陣はこうした研修の意義をしっかり理解してくれています。「これはいつか必ずやらなきゃいけないよね」と考え、惜しみなく投資してくれる。
その上で、会社として目指している姿としては、「大きくピボットできる組織」になってほしいという想いがあります。もちろん、今やっていることをしっかり継続して、お客さまに価値を提供し続けることは大前提です。しかし、それだけでは不十分でもあります。
世の中はどんどん変わっていきます。私もアメリカに駐在していて、大統領が変わるだけで社会の空気や価値観がここまで一変するのか、という驚きを肌で感じてきました。これからの時代、さらに変化のスピードは加速するはずです。自分たちも柔軟にアップデートできるような人材育成、組織作りがこれからの時代には不可欠になるはずです。
つまり、「変わるべきところを、ちゃんと変えられる会社」になっていきたい。
私たちの社名には、「イノベータ(Innovators)」が含まれています。では、自分たちは本当にInnovatorsでいられているだろうか? その問いに正面から向き合って、その名にふさわしい存在でありたい。この研修プログラムが、そうした未来につながる大事な一歩だと信じています。