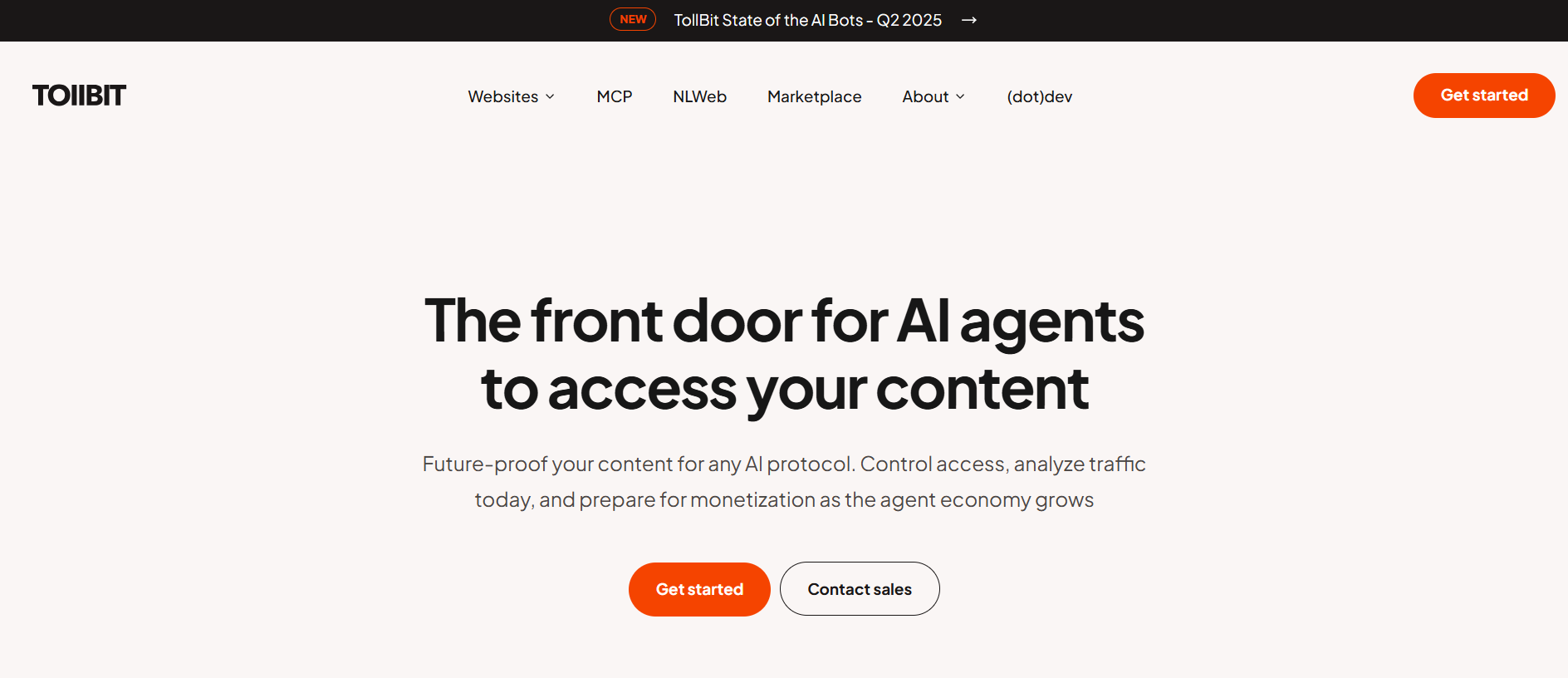目次
・記事の広告収入をAI検索から守る
・「通行料」を課金する仕組み
・トールビットを創業した理由
・「日本市場に参入するタイミングが来た」
記事の広告収入をAI検索から守る
―トールビットは出版社や新聞社のネット上での広告収入を、AI検索から守るスタートアップです。欧米でも日本でも、マスメディアがAI企業を提訴する動きが広がっていますが、トールビットのようなサービスが求められている理由はなんでしょうか。
パニグラヒ:AI検索が日常になると、人間が新聞社・出版社のウェブサイトを訪れなくなり、彼らの広告収入が激減するからです。
基本的に、AI企業各社は「我々はグーグルと同じだ」と主張してきました。グーグルが新聞社・出版社のコンテンツを自由に行き来し、ユーザーを検索からサイトまで誘導するように、AIもネット上に公開された記事をボットが読み込み、(出典を明記する形で)ユーザーに表示する。「だから我々(AI企業)の仕事も、原理的にはグーグルと変わらない」と言ってきたわけです。
ところが、コンテンツを提供する新聞社・出版社の目から見れば「収益性」という観点において、両者の差は歴然としています。出版社の協力を得て、45日間のAI検索とグーグル検索の収益率の差を調査した結果をお伝えしましょう。
グーグル検索においては、クローラー(記事を読み込むロボット)が3,000万回以上、出版社の記事を読み込んで検索画面に表示させたことで、数千万人以上の「人間の訪問者」を得ていました。人間の訪問者が広告をクリックすることで最終的に出版社が収益を得られます。
ところがAI企業による検索では、AIのボットが記事を読み込んだ回数は約1,300万回で、最終的にサイトを訪れた「人間の訪問者」はなんと650件。人間がAIを通して情報を入手する際、AIは「掲載された記事を読み込んで、ユーザーの質問の意図に沿った形で回答を成形する」ことから、ボットが読み込んだ元記事への流入が極端に落ち込んでしまうのです。
つまり「AIが記事を読み込んで、回答を出す」時代において、出版社は人間の読者を呼び込めなくなってしまい、結果的に広告収入が激減する。トールビットはこの大きな問題を解決しようとしています。
ジョスリン:現在のAI検索と出版社の関係性は、20世紀初頭に社会問題となった「ナップスター」現象と似ています。P2P技術を用い音楽を無料でダウンロードできたこのサービスは、著作権を持っている音楽家の収益を奪いました。AIも、プロの記者・編集者たちが制作したニュースをAIが無料で読み込み「人間の訪問者」を奪ってしまう。その後、音楽業界でスポティファイ(Spotify)が出てきて、音楽家が守られたように、新聞社・出版社の収益を守るサービスが必要とされています。


「通行料」を課金する仕組み
―では、トールビットは具体的にどのようにして新聞社・出版社の収益を確保しているのですか?
パニグラヒ:AIが記事を読み込む際の「通行料」を課金する仕組みを作りました。トールビットはAI企業と出版社の間に入り、AI企業が出版社の記事をどれくらい読んだか、APIやアクセスログを通して把握します。その上で記事の利用料に応じて、出版社がAI企業に課金する、という仕組みです。
ジョスリン:トールビットを使うと、コンテンツ企業は「AIがどれだけ自社の記事を利用しているか」を数値的に把握できるようになります。「どのAIがどれだけ私たちの記事を読んでいるのか」「どれくらいの頻度か」「どんな記事か」などといったデータを確認できるのです。
こうした正確なデータをもとに、出版社はAI企業との契約交渉や価格交渉を合理的に行うことができるようになったのです。
パニグラヒ:実際、出版社はこれまで、AI企業が自社コンテンツをどれくらい使っているか、数値として把握できていなかったのです。トールビットのレポートを見て「あれ、これまでAIは私たちの記事を『トレーニング』用途で使っていると思っていたけど、すでに数百万回も使っているじゃない」と気づいた出版社もいます。
往々にしてAI企業は出版社に「包括契約」という形で一括で記事使用料を支払おうとしますが、出版社側は「トールビットで確認できた訪問数に合わせて、適切な金額を要求する」という防衛策を講じられるようになったのです。
一方で、私たちはAI企業を「悪者扱い」する立場をとっていません。AI企業にも正当な懸念や現実的な課題があるからです。現在のAI検索をめぐる情勢は、1995年のウェブ黎明期だと形容できるかもしれません。つまり、人々はAI検索を求めている(95年に大衆がウェブ上で無料で記事を読めることを望んでいた)のに、AIボットに対する適切な使用料(95年当時は広告モデル)がまだ開発されていません。
私たちはAI企業、コンテンツ企業と共に、両者がサステナブルにビジネスを行える仕組みを作りたいと願っています。
image : TollBit HP
トールビットを創業した理由
―お二人は以前、飲食店向けPOSシステムを開発するトースト(Toast)で勤務していました。トールビットを共同創業したきっかけについて教えてください。
ジョスリン:私はトーストを退職後、AI関連の企業でWebスクレイピング(Webサイトから情報を抽出するソフトウエア技術)とGPT技術の実装に携わっていました。企業の購買プロセスを自動化し、フォーチュン1000企業の調達を支援していたのです。
私の仕事ではWebスクレイピングがプラスに働いていましたが、今後「Webスクレイピングが実害を与えるケースが出てくるだろう」と感じていました。その時、トーストで広告の仕事をしていたパニグラヒから連絡があり、「広告チームでもう一度仕事をしないか」と誘われたのですが、2人で「AIと広告の未来」について結果的に語り合うことになったのです。
パニグラヒ:実際、広告ビジネスもAIの台頭で打撃を受けていました。「インターネット上で、人間ではない新しいタイプの訪問者が生まれつつある」ことに対して、メディア業界は丸腰だったのです。AIに対して「価値を交換できる仕組み」を作ろうと意気投合し、トールビットを立ち上げました。

image : Summit Art Creations / Shutterstock
「日本市場に参入するタイミングが来た」
―日本市場に参入する考えはありますか。
ジョスリン:日本市場には高いポテンシャルを感じています。1年以上前に、日本の出版社から連絡を受け、AIによるスクレイピングや著作権の問題についての質問を受けています。
アメリカの多くの出版社よりも、AIについて理解しているという率直な印象を受けました。日本市場に参入するタイミングが来たと考えています。
協業に際しては、供給側(コンテンツ産業)と需要側(AI企業)のいずれか、もしくは両方を支援できるあらゆる企業に関心を持っています。
供給側では出版社やウェブサイト運営社、テクノロジー企業、出版支援をしているコンサル企業などです。需要側では、AI関連のテック企業やAI企業とのネットワークを持つ企業も興味深いと考えています。
パニグラヒ:日本では日本経済新聞と朝日新聞が25年8月にパープレキシティを提訴しましたよね。アメリカではダウ・ジョーンズが24年に同社を提訴しています。つまり、1年前のアメリカの位置に今、日本はいるわけです。ここから日本での需要は急速に高まると感じています。
出版関連にとどまらず「AIエージェント(ボット)が実際に行動をとるWebサイト」にも関心があります。例えば、食事の予約サイトなどはアメリカでも当社への関心が高まっています。
―協業の際、重要視する形態はありますか。
パニグラヒ:最も優先すべきは「共同開発」でしょう。出版社のニーズに合わせて、ともにトールビットの活用方法を考えたいと思っています。ある出版社は訴訟を望み、違う出版社は1対1の契約を求めています。「Webサイトのクロール(AIボットによるサイトへの巡回)は許可するけれども、そのためのお金を支払いたくない」という出版社もあれば「巡回するなら課金しろ」というスタンスを打ち出す企業もあります。
私たちは顧客に「このようにビジネスを運営しろ」と指図するつもりはありません。出版社の事情に合わせて、柔軟に対応します。
次に流通という関係性でしょう。日本の市場と文化を熟知しているコンサルタントと組みたいと考えています。
―最後に、日本企業の読者に伝えたいことはありますか。
パニグラヒ:まずコンテンツ産業の皆さんにお伝えしたいのは「AI時代は実は大きなチャンスである」ということです。
AIの台頭により、インターネット上の経済構造が大きく変わろうとしています。ここで大事なポイントは「AI企業自身も、まだ答えを持っていない」ということです。AI企業自身が「新しいルール」を決める前に動き出し、答えを見つけ出せば、自社に有利な環境を作ることができます。逆に3年このまま何もしないと、AI企業が条件を決めてしまうでしょう。
ジョスリン:パニグラヒが言ったように、暗い話が全てではありません。AIの台頭で「コンテンツ消費量」は爆発的に増えるからです。というのは、AIは人間のように記事を読んでいる途中で飽きることもありませんし、無尽蔵に記事を読み込めます。
人間とAIの両方が生む出すコンテンツ消費の総量が、これから爆発的に増えていくでしょう。出版社やコンテンツ製作者が正しく環境を整備できれば、極めて健全で新しいエコシステムを築くチャンスが目の前に広がっているのです。