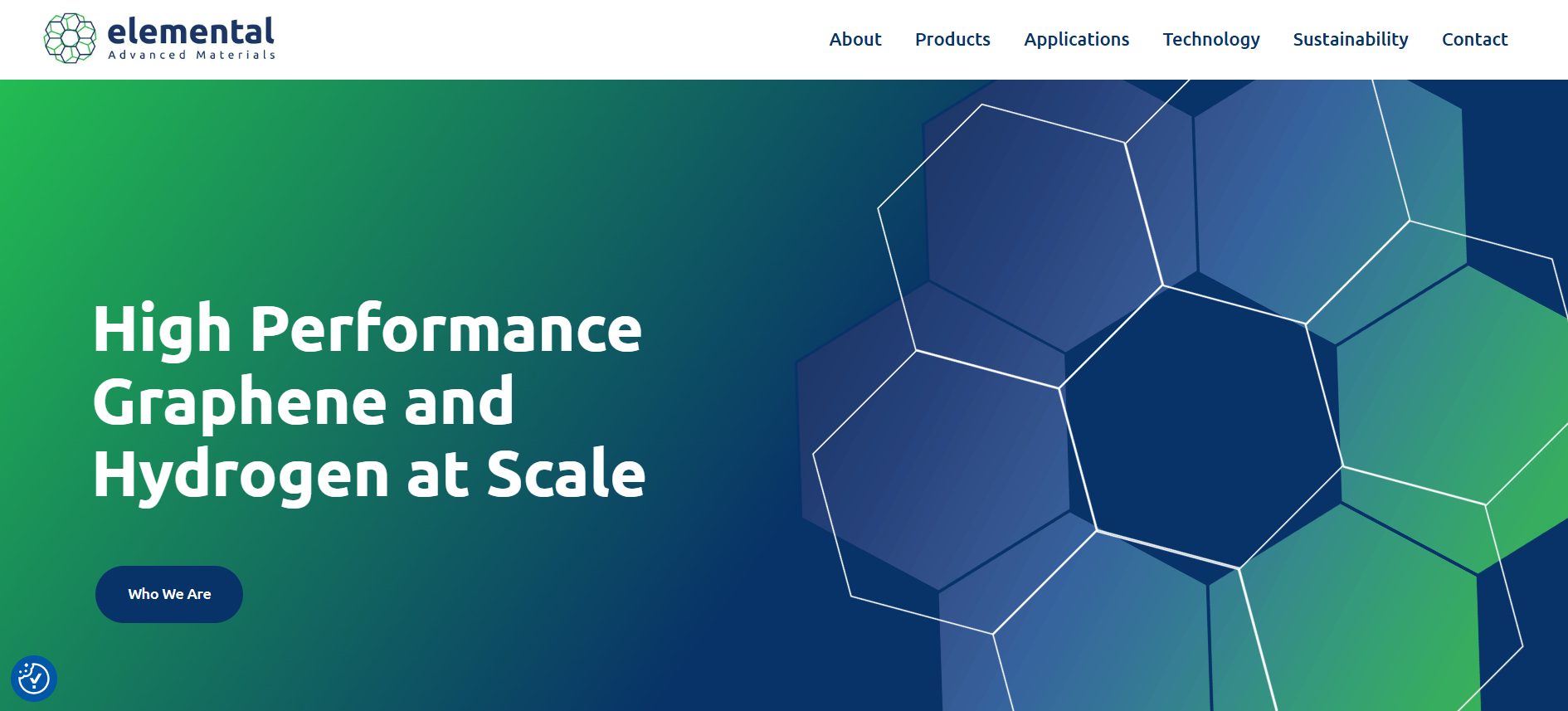目次
・偶然発見した「廃プラからグラフェン」
・廃プラを単一工程でカーボンナノオニオンに変換
・「既存プロセスの数百倍」の生産効率を実現
・「夢の素材」グラフェンへの不信感をどう乗り越えるか
・日本市場への期待「電話してください、誰とでも話します」
偶然発見した「廃プラからグラフェン」
ビショップ氏は金融畑の連続起業家で、エレメンタルは自身にとって5度目のオーナー・オペレーター企業となる。「会社を創業したり運営したりするのは私にとって特別なことではありません。ロンとはこれが4〜5回目の共同プロジェクトです」(ビショップ氏)
一方、プレスウッド氏はNASAで軌道上構造物の設計に携わった経験を持つ機械エンジニアだ。「医療機器から環境分野まで、幅広い開発プロジェクトに関わってきました。廃棄物の再生事業を調べていた際に“なぜ既存の手法はうまくいかないのか”を突き詰めた結果、炭化水素――つまりプラスチックなどをアップサイクルする方法に行き着いたのです」(プレスウッド氏)
ビショップ氏によれば、この技術の原点は16年前のアイデアにさかのぼる。
「温室効果ガス、二酸化炭素、揮発性有機化合物(VOC)、プラスチック、電子廃棄物など多様な廃棄物処理に対して特許を保有しています」(ビショップ氏)
転機が訪れたのは約3年前。廃プラスチックを処理した際、偶然にもグラフェン(後にカーボンナノオニオン)が生成されていることを発見した。
「最新のバージョン2の機械では、廃プラスチックからカーボンナノオニオンと水素が安定して生成できるようになりました」(ビショップ氏)


廃プラを単一工程でカーボンナノオニオンに変換
エレメンタルの革新性は、廃棄プラスチックを単一工程で高機能なカーボンナノオニオンへ変換できる独自プロセスにある。
プレスウッド氏は、同社が生成するカーボンナノオニオンの特徴を次のように説明する。
「ナノオニオンは、サッカーボール状の炭素分子がタマネギのように多層構造を形成した材料です。電子顕微鏡で観察すると、タマネギを輪切りにしたような同心円状の層が確認できます」(プレスウッド氏)
この多層構造こそが、さまざまな素材の性能を向上させる源泉だ。
「ナノオニオン表面の sp²/sp³ 結合は導電性を持ち、かつ他の素材と強固に結合します。そのためコンクリートや樹脂、ポリウレタンなどに添加すると強度が大きく改善します」(プレスウッド氏)
さらに、プロセスの最大の特長は環境負荷ゼロであることだ。「私たちのプロセスはCO2を排出しません。廃プラスチックを投入すると、その炭化水素が分解されますが、大気中に追加のCO2を放出することなく、炭素材料と水素を回収できます。通常ならメタン(CO2の26倍の温室効果)を発生させる廃棄物を、価値ある素材へアップサイクルできるのです」(プレスウッド氏)
2025年9月現在、エレメンタルは米テキサス州の拠点で、生産機の最終調整を進めている。装置は大型SUVほどのサイズで、1台で1日あたり9,000kgのカーボンナノオニオンと900kgの水素を生産する設計だ。
「現在は本格稼働前ですが、すでに顧客向けのサンプル提供を通じて、有望な実証データが得られています」(ビショップ氏)
実際に得られた性能改善の例は以下の通りだ。
・アスファルト:低品質のビチューメンが高性能化
・コンクリート:圧縮強度 20%向上
・ポリウレタンフォーム:難燃性 20%向上
さらに、樹脂分野では特筆すべき成果も出ている。「樹脂材料では、圧縮強度・引張強度がともに60%向上し、弾性率も55%改善しました」(ビショップ氏)
こうした大幅な性能改善を、わずかな添加量で実現できる点もナノオニオンの強みである。
「これらの結果は重量比1%未満の添加で得られたものです。大量に加える必要はなく、非常に少量で大きな効果が表れます」(プレスウッド氏)
アップサイクルされた廃プラスチック由来の炭素材料が、既存素材の性能を飛躍的に高める――エレメンタルの技術が注目される理由がここにある。
「既存プロセスの数百倍」の生産効率を実現
エレメンタルのプロセスは、既存のカーボンナノオニオン製造法と比べて圧倒的な生産性を持つ。プレスウッド氏は、従来法との差を次のように説明する。
「ナノオニオンを作るプロセス自体は存在します。ナノダイヤモンドやダイヤモンド粉末をトレイに入れ、それをオーブンで1700℃まで3日間加熱する方法です。しかし、私たちはそのプロセスで『1年かけて作る量』を1時間で生産できます」(プレスウッド氏)
加えて、ビショップ氏はエレメンタルの独自性は生産効率だけではないと強調する。
「私たちのようにCO2中立、もしくはCO2マイナスで、なおかつ廃棄物ゼロのプロセスは他にありません」(ビショップ氏)
さらに、このプロセスは入力素材の制約もほぼない。
「PVC、塗料が付着したプラスチック、臭素化プラスチック、ポストコンシューマー廃棄物――何を入れても問題なく処理できます。しかもすべてが価値ある生成物になります」(ビショップ氏)
同社はまだプレ・レベニュー段階だが、市場からの注目は大きい。ビショップ氏は次のように語る。
「グローバル500社のうち75社とNDAを締結しており、日本企業とも複数交渉を進めています」(ビショップ氏)
多くの企業はエレメンタルの技術に強い関心を持ちながら、まずは安定量の供給を見極めようとしている。
「多くの方が製品に興味を示しています。必要なのは、一貫した量と品質を示すこと。私たちが生産に入れば、材料調達の検討が本格化します。ただし、そのためには機械を稼働させることが前提です」(ビショップ氏)
カーボン系ナノ材料は、過去に期待ほど性能が出なかった例が多く、その経験から新規採用に慎重な企業は多い。ビショップ氏は、ある世界トップ10化学メーカーの反応をこう振り返る。「最初は『すでに試したので興味はない』という反応でした」(ビショップ氏)
だが、エレメンタルのナノオニオンを実際に評価した結果、状況は大きく変わった。「1つ目の研究所でテストし、2つ目の研究所で再テストし、現在は3つ目の研究所で検証中です。その結果に基づき、エポキシ樹脂への適用に向けた発注(PO)が予定されています」(ビショップ氏)
過去の「グラフェン失望」の記憶を乗り越え、世界の大手企業が次々に採用検討へ踏み出している。
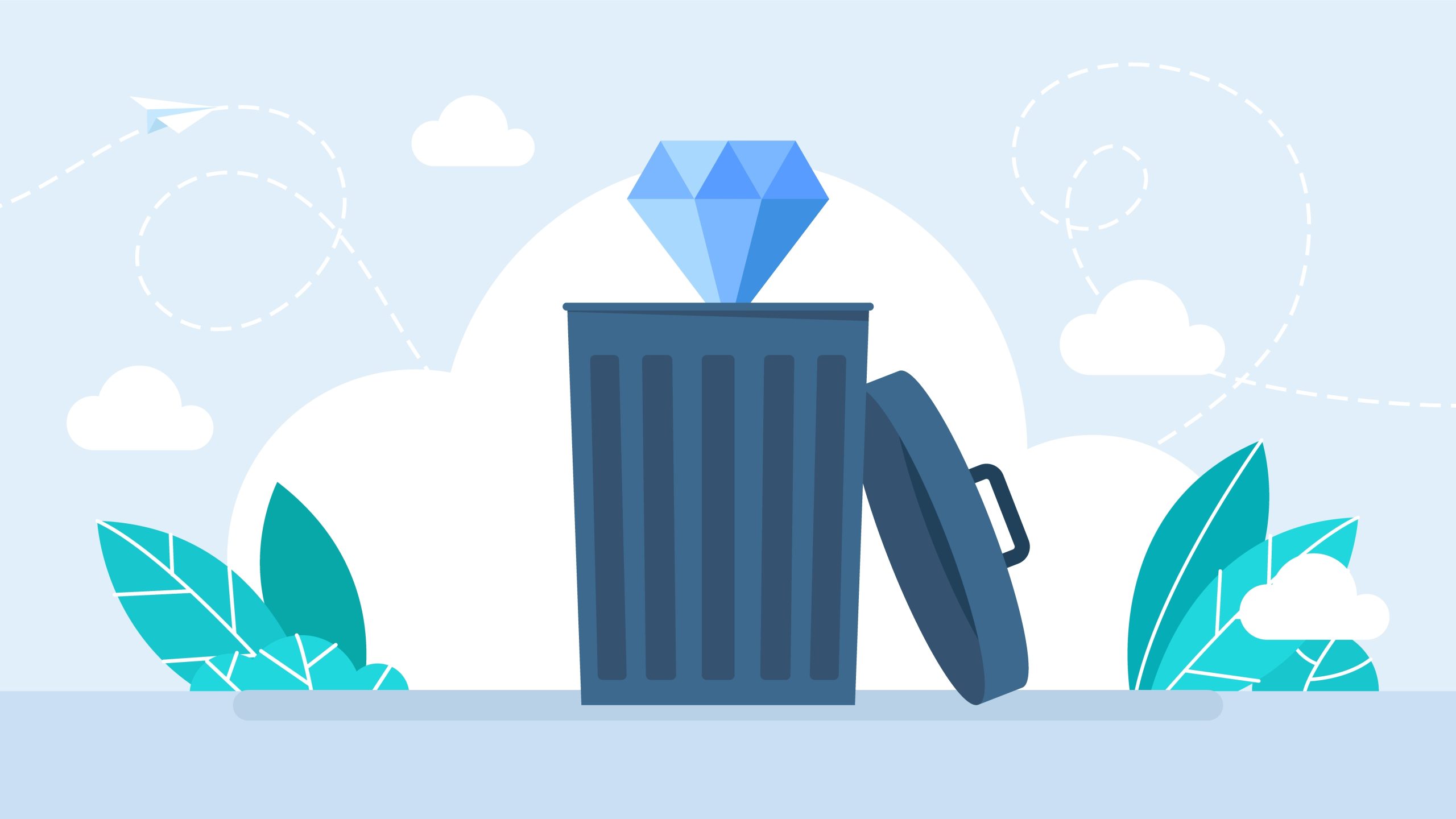
image : Yuriy2012 / Shutterstock
「夢の素材」グラフェンへの不信感をどう乗り越えるか
エレメンタルが直近で目指すのは、量産機の安定稼働だ。プレスウッド氏は、課題克服に手応えを感じている。「私たちの目標は機械を稼働させることです。予期しない問題に直面してきましたが、先週のテストで良い結果が得られ、このハードルを越えられたと考えています」(プレスウッド氏)
ビショップ氏も、量産フェーズの具体的な数字を挙げる。「1時間あたり200〜800kgのナノオニオンを生産することが現在の目標です」 (ビショップ氏)
量産機が稼働すれば、大きなボトルネックは市場側に移る。プレスウッド氏は、その難しさを率直に語る。「最大のハードルは顧客の認知です。これまで『グラフェンは夢の素材』と言われながら、実際に試すと期待外れだった例が多く、企業は慎重になっています」(プレスウッド氏)
過去の落胆によって生まれた不信感をいかに乗り越えるかが、エレメンタルの市場浸透の最初の関門となる。
しかし、初期段階の成果はすでに見え始めている。ビショップ氏は、今後の事業展開を段階的に説明する。
「最初の売上はコンクリートとアスファルトになるでしょう。生産さえ始まれば、すぐにアスファルト分野で販売できます」(ビショップ氏)
その後は、安全性要件の比較的低い用途から順に評価が進む見通しだ。
・プラスチック
・ポリマー
・コーティング
・潤滑剤・オイル添加剤
「これらは6〜18カ月以内に採用が進むと見ています。一方で、電池やキャパシタといったエネルギー分野は、長期的・多段階の検証が必要なため、さらに時間がかかるでしょう」(ビショップ氏)
コンクリートやアスファルトのような早期市場から入り、より厳格な品質要求を持つ分野へ順次展開していく――それがエレメンタルが描く市場浸透のロードマップだ。
日本市場への期待「電話してください、誰とでも話します」
日本企業との協業について、ビショップ氏は強い関心を示す。「合弁事業やライセンシング、化学会社、プラスチック会社、電池会社、自動車メーカーなど、幅広い分野との協業を検討しています」(ビショップ氏)
その理由のひとつは、日本が持つ多様な応用領域との相性の良さだ。「自動車の樹脂部品に使えば30%軽量化できますし、タイヤにナノオニオンを入れれば耐摩耗性の向上と乗り心地の改善が期待できます」(ビショップ氏/プレスウッド氏)
エレメンタルの技術は、地域で発生する廃プラスチックをそのまま高付加価値素材へと変換できるため、素材の地産地消モデルを構築しやすい。「人口15〜20万人の都市なら、1台の機械を稼働させるのに十分なプラスチック廃棄物が出ます。つまり、素材を必要とする工場の近くで生産できるのです」(ビショップ氏)
日本国内の多数の自治体規模を考えると、このモデルが広く展開できる可能性は大きい。
長期的には、グローバル市場での大手企業との戦略的パートナーシップが成長の鍵となる。ビショップ氏は「昨年、一昨年、60億ポンドのグラファイトがブレーキから電池まで使用されました。2030年までに、電池の需要により、その数字は160億ポンドになると予想されています」と市場拡大への期待を語る。
この急拡大する需要に対応するには、グローバルな展開が不可欠だが、同社単独では限界があることも認識している。「日本、韓国、米国全土、ヨーロッパ全土に機械を設置する必要があります。しかもそれは電池市場だけの話です」
そのため、戦略的なパートナーシップが鍵となる。「私たちのような規模でグローバル展開できるでしょうか?おそらく私たちより大きな企業との連携が必要でしょう。ただし、私たちは確実に最初の5台または10台の機械で実績を作ることができます」
最後に、ビショップ氏は日本の潜在的パートナーへ力強いメッセージを送った。
「まず電話してください。ロンと私が誰とでも話します。私たちが持つ、炭素市場や廃棄物市場に対するグローバルソリューションについて話しましょう」
image : Elemental Advanced Materials HP