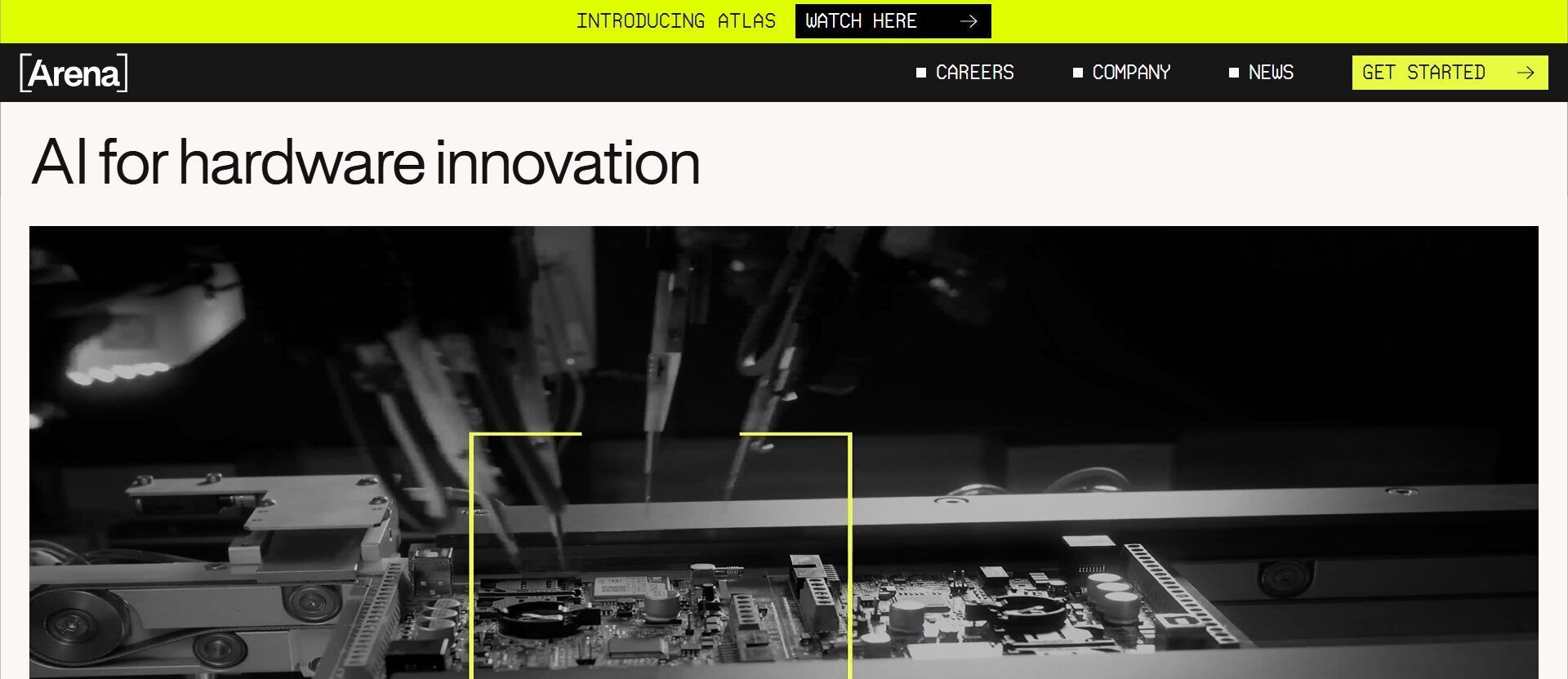目次
・マッキンゼーやパランティアを経て創業
・「映画に登場したAIアシスタントを現実に」
・アリーナが開発したAIエージェントの強みとは
・生成AI時代は「作る」より「検証」がネック
・トップ企業から広げる「ナイキ型アプローチ」
・「自己修復マシン」が実現する!?
・ものづくりの国ニッポンへの期待
マッキンゼーやパランティアを経て創業
ラナーデ氏のキャリアは、ハードウェアとは一見かけ離れたところから始まった。スタンフォード大学で物理学を学び、コロンビア大学大学院では応用物理学の博士課程を修了。専門は量子力学、とりわけ磁性を量子論的に解析する研究に取り組んだ。
「10年間は物理学と応用物理学に没頭しました。その後、意外かもしれませんがビジネスの世界に飛び込んだのです」
博士号取得後に選んだのは、経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーだった。
「マッキンゼーで学んだのは、フォーチュン500企業のような複雑な大組織がどう機能するか、どんな問題を抱え、どう価値を創造するかでした。私には経済学やビジネスの背景が全くなく、純粋に科学と数学の世界にいたので、この経験が重要でした」
この時の経験は、のちにアリーナの事業戦略を形づくる重要な基盤となる。
2014年には、自身初の技術系スタートアップ、キモノ・ラボ(Kimono Labs)を創業。インターネット上の情報を自動で収集・整理する「知的ウェブスクレイパー」を開発し、ピーター・ティール氏やサム・アルトマン氏、Yコンビネーターから投資を受け、15万人以上のユーザーを獲得するまでに成長した。
「キモノ・ラボの時代には、チームで1カ月間日本に滞在したこともあります。当時、サービスは非常に人気を集めていました」とラナーデ氏は振り返る。
2016年にキモノ・ラボは米データ分析企業パランティア・テクノロジーズ(Palantir Technologies)に買収され、ラナーデ氏は同社で2年間勤務。この経験も大きな財産となった。
「パランティアもマッキンゼーも、フォーチュン500のような大企業にソリューションを提供していました。アリーナを立ち上げるとき、最初の発想は『高度なAIを複雑な組織に提供する』ことでしたが、私たちはその焦点をさらに絞り、ハードウエア、特に電気工学に特化することにしました」
そして2019年、ついにアリーナを創業。
「物理学で培った電気工学の知識、マッキンゼーで学んだ大企業の構造理解、パランティアでのソフトウエア応用の経験――。この3つの背景すべてが合流したのがアリーナです。私にとって、まさにキャリアの集大成といえる存在です」
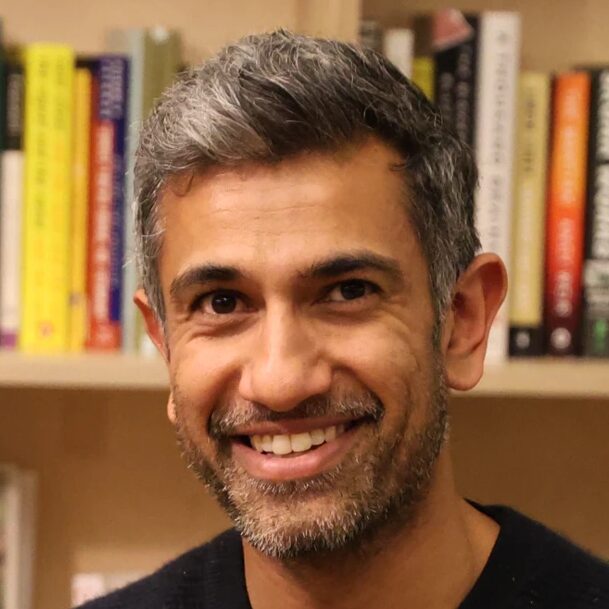
「映画に登場したAIアシスタントを現実に」
アリーナが挑む課題を説明する際、ラナーデ氏は映画『アイアンマン』を例に挙げる。
「主人公トニー・スタークがハードウエアを開発するとき、彼にはJarvis(ジャーヴィス)というAIアシスタントがいます。私たちは、そのJarvisを現実に作ろうとしているのです」
この比喩の裏には、ソフトウエアとハードウエア開発の決定的な格差がある。
「この50年間はソフトウエアの黄金時代でした。フェイスブック、インスタグラム、グーグルといった企業の登場で、ソフトウエア開発は飛躍的に容易になりました」
一方で、ハードウエア開発は依然として遅く、手作業に依存している。
「ものづくりで最も重要なのは、設計・テスト・修正という反復サイクルの速さです。ソフトウエアはこのサイクル(REPL:Read-Eval-Print Loop)が劇的に加速しましたが、ハードウエアははるかに遅いのです」
実際、電気工学は現代ハードウエアの不具合の4〜5割を占める原因となっており、人材面でもソフトウエアエンジニアが90%増えた一方で、米国では電気エンジニアが20%以上減少している。
「テスラやリビアン(Rivian)、スペースX(SpaceX)のような企業ですら電気工学の人材は不足しています。AIなしには、次のハードウエア革命は起こせないのです」
アリーナが開発したAIエージェントの強みとは
アリーナのAIエージェント「アトラス(Atlas)」の強みを理解するには、現代の電子機器が持つ3層構造を知る必要がある。最も内側にあるのがチップ、その外側にあるのがプリント基板(PCB)、さらにその外側で複数の基板をつなぐシステム配線だ。
ラナーデ氏は戦闘機を例に、この構造における電気系統の重要性を示す。
「1960〜70年代の戦闘機では、最も高価な部品はジェットエンジンでした。しかしF-35では違います。最も高価なのはアビオニクス(航空電子機器)なのです」
アビオニクスの費用はF-18からF-35への進化の過程で10倍に膨らんだという。電子機器はまさに「現代ハードウエアの神経系」となっている。
従来の問題解決は極めて非効率だ。たとえば新車のテストでライトが点灯しなければ、電気技師は座席やカーペットを外し、何キロにも及ぶ配線をたどって原因を探す。丸一日かかることもあり、その過程で車体を傷つけてしまうリスクさえある。
ここに、アトラスの革新性がある。
「アトラスは回路図や電気接続をすべて理解しており、異常の原因がどこにあるかを特定できます。そして技師に『このパネルだけを開けて、このピンを確認してください』と具体的に指示します」
専門知識を技師個人に頼るのではなく、AIが持つことで効率と正確性が飛躍的に高まるのだ。
生成AI時代は「作る」より「検証」がネック
アトラスの開発でラナーデ氏が最も重視しているのは「検証」の自動化だ。この点こそが、アリーナを他社と一線を画す存在にしている。
「生成AIによる『作る』ことは、今や簡単で安価になりました。ChatGPTを使うように、回路の設計を生成することもできます。しかし、本当に重要なのは『良い設計』かどうかを確かめること。ボトルネックは生成ではなく、検証にあります」
AIが大量の設計を生み出す時代、価値を持つのは「正しく動く設計」だ。アリーナは設計がシミュレーションから現実へと移るテスト段階に注目し、そのギャップを埋める仕組みを構築している。
「アトラスはシミュレーションとテストから学び、両者を橋渡しすることにフォーカスしています」
さらに、独自の電磁気学モデルと言語モデルを組み合わせることで、アトラスは英語や日本語での対話に加え、視覚的なインターフェースも備える。
「画面の3分の2はビジュアルです。設計図やデータを見ながら、エンジニアはアトラスと対話します。とても使いやすく、現場から高く評価されています」
トップ企業から広げる「ナイキ型アプローチ」
アトラスの効果は、すでに顧客の現場で実証されている。
ある工場では、新車の電気テストに失敗した際、入社したばかりの新人エンジニアがアトラスに相談。ARインターフェースを用い、わずか6分で原因を突き止めた。本来であれば6時間かかる作業だった。
「専門知識をAIに持たせることで、経験の浅いエンジニアでも高度なトラブルシューティングが可能になります」
航空宇宙分野でも同様の成果が出ており、テスト工程の効率化によりチームの開発速度が飛躍的に高まった。全体として、テスト段階での工数を35%以上削減できているという。
アリーナの成長戦略は、いわゆる「ナイキ型アプローチ」だ。
「私たちはアマゾンではなくナイキのようになりたい。ナイキがマイケル・ジョーダンを起用してブランドを広めたように、まずは業界のトップ企業に導入してもらって実績を積み、市場全体に広げていく戦略です」
従来のスタートアップが小規模企業から大企業へと展開していくのとは逆で、アリーナは最初からフォーチュン500企業に照準を合わせている。AMDをはじめとする先進的な企業がすでに採用しており、「今後6〜12カ月でハードウエア界のマイケル・ジョーダンが登場する」とラナーデ氏は自信を見せる。
成長スピードも加速している。過去半年で社員数は2倍に拡大し、需要に供給が追いつかないほどだ。既存顧客の利用拡大も顕著で、あるフォーチュン500企業はわずか1年で支出を10倍に増やしたという。
image : Arena HP
「自己修復マシン」が実現する!?
ラナーデ氏が描く長期ビジョンは、一見SFのような世界だ。キーワードは「自己修復マシン(Self-healing machines)」。
「現在の私たちはJarvisのように、エンジニアがハードウエアを理解し、テストやデバッグを行えるよう支援しています。自己修復マシンの第一歩は、AIをハードウエアそのものに組み込むことです」
彼が思い描く未来は段階的に進む。まずは、機器がユーザーに「どう対処すべきか」を自ら指示する段階だ。「今は私たちがドローンを操作しますが、将来的にはドローンが自分の不具合を説明し、修理方法を教えてくれるべきです」
次の段階では、映画の爆弾処理班のように「赤い線を切れ」といった指示を、機器自体が人に伝えるようになる。そして最終的には、ヒューマノイドロボットとの組み合わせで「機械が自ら自分を修理する」世界を目指している。
このビジョンが特に重要になるのは、人類の活動領域が地球を超えたときだ。
「月面基地の建設や火星探査、小惑星の植民地化や深海基地の建設といった厳しい環境では、機器は頻繁に故障します。だからこそ、自己修復システムが不可欠になるのです」
ものづくりの国ニッポンへの期待
ラナーデ氏はまた、日本市場への展開にも強い関心を示す。
「日本のエンジニアリング文化を深く尊敬しています。日本は世界に優れたハードウエア技術を数多く生み出してきました」
特に注目するのは、人口減少・高齢化が進む中でAIを活用し、競争力を維持する道だ。
「AIを活用すれば、日本企業は伝統的な強みを最先端技術と融合させ、今後も競争力を発揮できるはずです」
想定する協業先は、半導体やPCB関連の電子機器メーカー、航空宇宙・防衛、自動車、ロボティクスを含む重工業など幅広い。戦略はあくまで「一社とのパートナーシップ」から始めることだという。
「これまでの顧客には、新技術に賭ける先見性あるリーダーがいました。その賭けはすでに成果を上げています。日本でも、そうしたリーダーが1人いれば十分に市場参入のきっかけになるのです」