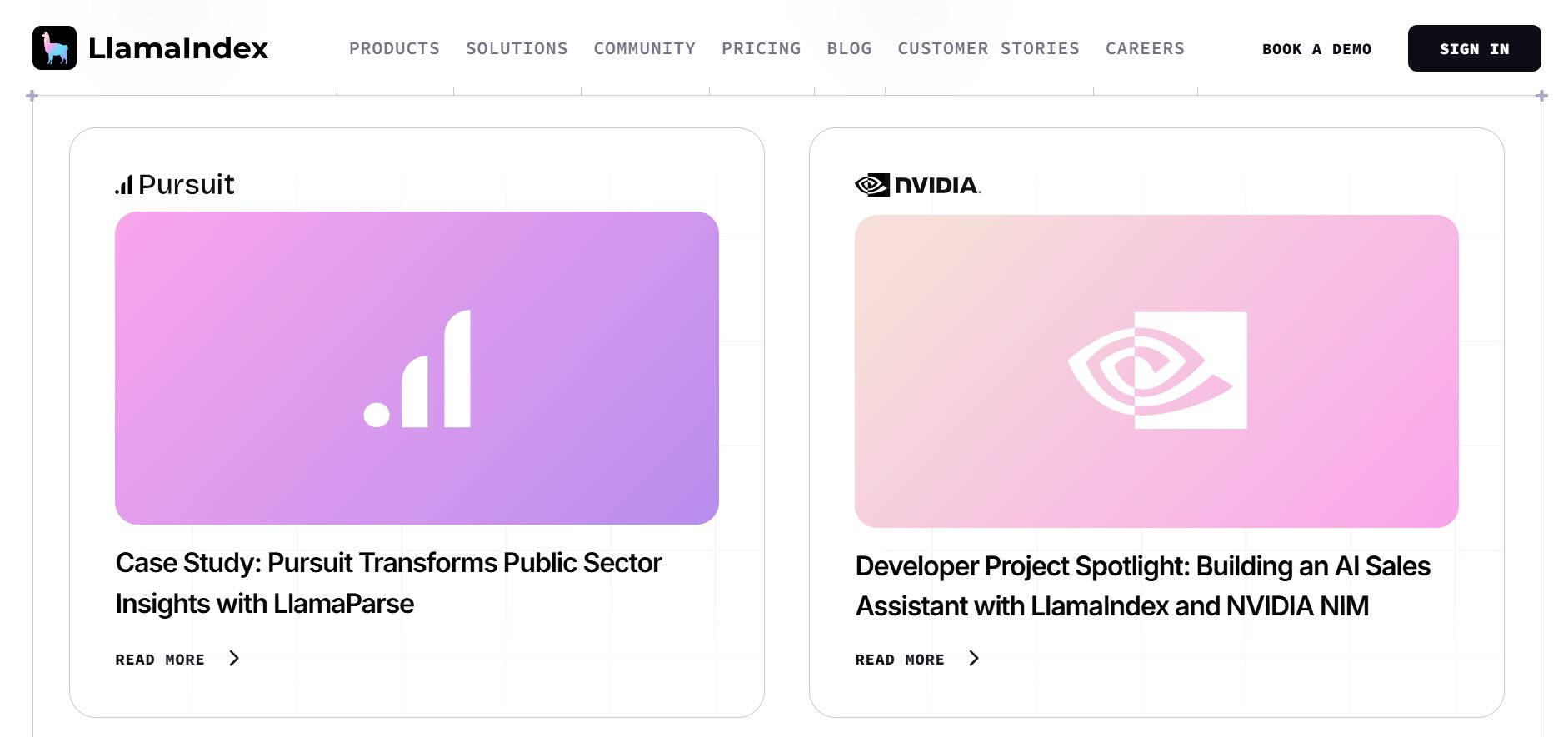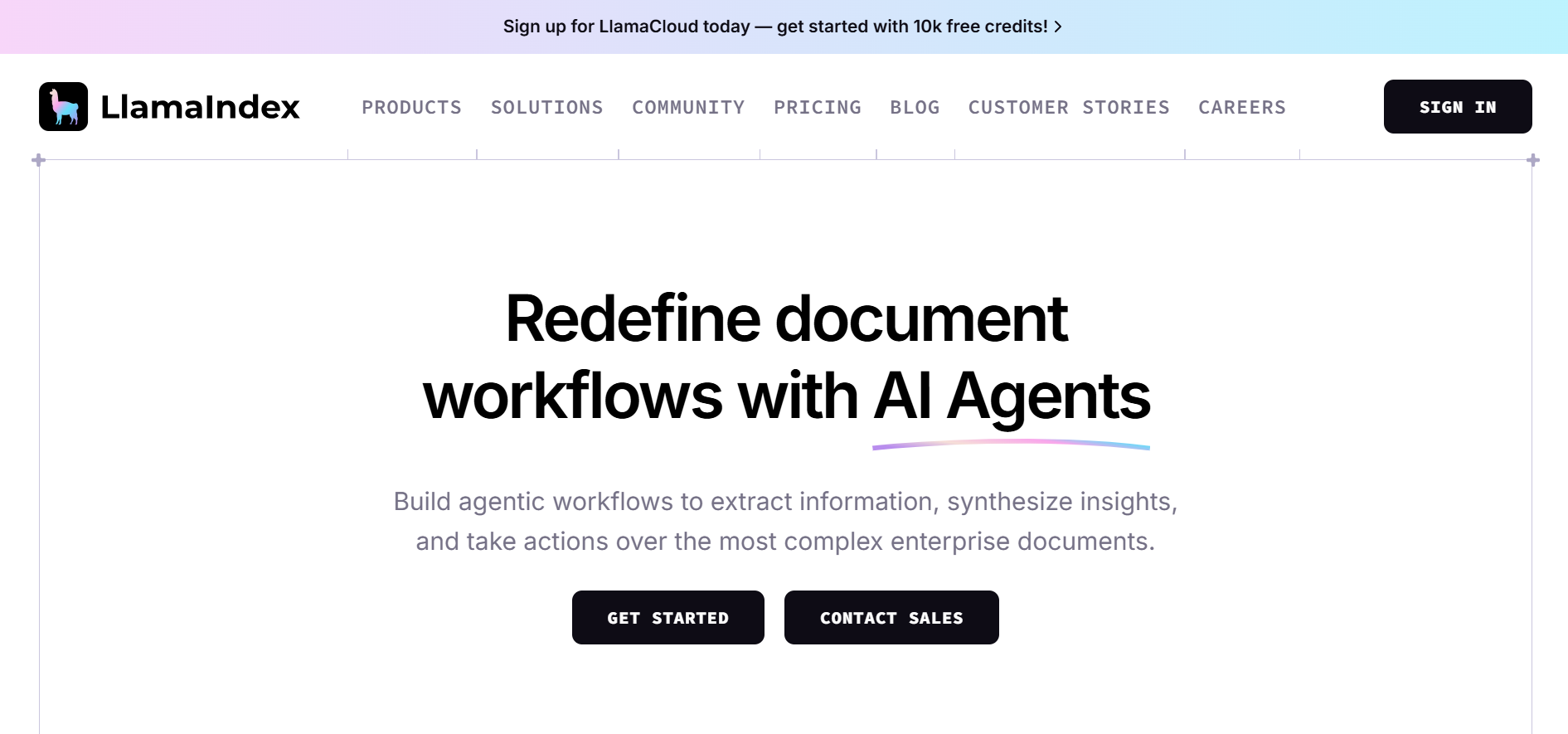目次
・“眠れる文書”を活かす挑戦
・無料版→有料版ではないビジネスモデル
・日本では楽天も導入、チャットツール構築
・目指すのは知的作業の“自動化インフラ”
・日本市場にも大きな関心、課題はブランド認知
“眠れる文書”を活かす挑戦
AI業界の第一線で培った経験から、ある根本的な課題に気づいていた。企業内に蓄積されている大量の文書やファイル――いわゆる「非構造化データ」が、十分に活用されていない現実だ。
自動運転技術で知られるUber ATGでは、2年半にわたって深層学習モデルの研究に従事。さらにQuoraでは大規模なレコメンデーションシステムを開発し、AIスタートアップのロブスト・インテリジェンス(Robust Intelligence)ではAI部門を率いた。こうした豊富なキャリアの中で、リウ氏の中には「自分の会社を立ち上げたい」という思いが常にあったという。
転機が訪れたのは2022年。OpenAIが開発したGPT-3の登場で生成AIが注目を集める中、多くの人々がそれをビジネスに活用したいと考え始めていた。リウ氏は、企業内の情報――特に整理されていないPDFやパワーポイント資料のような“眠れる文書”とAIをつなぐことができれば、大きな価値を生み出せると考えた。
「GPT-3を社内データと接続できるようにするオープンソースプロジェクトを始めたんです。最初は、LLM(大規模言語モデル)と非構造化データソースをつなぐ基本ライブラリの構築から始めました」とリウ氏は語る。
このプロジェクトは開発者コミュニティで瞬く間に注目を集めた。多くのユーザーからの反響を受け、リウ氏は確信する。「これには確かな市場ニーズがある。企業がLLMを活用し、社内のリアルな業務文書とつなげるための本格的なプロダクトを作るチャンスだと思いました」
リウ氏は共同創業者として、ウーバー時代の同僚であるサイモン・スオ(Simon Suo)氏をCTOに迎えた。現在は、リウ氏がマーケティング・営業・経営全般を担当し、スオ氏がプロダクトとエンジニアリングの実装を担っている。
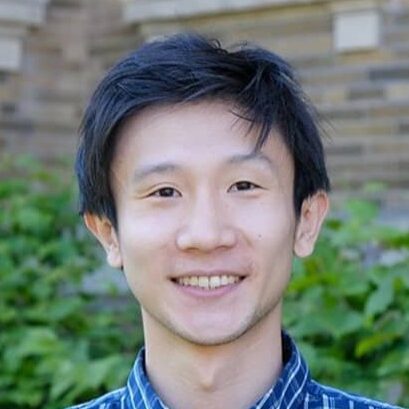
無料版→有料版ではないビジネスモデル
ラマ・インデックスのビジネスモデルは、一般的な「無料版と有料版」というオープンソース企業の定番戦略とは少し異なる。開発者向けのオープンソースツールと、企業向けのクラウドサービスという、性質の異なる2つの製品を両輪として展開しているのが特徴だ。
創業当初から提供しているオープンソースツールキットは、開発者が「RAG」型のAIワークフローを構築・統合するための道具箱のような存在だ。「質問への回答やアクションの実行、ツールの活用など、さまざまな推論エンジンを作るための機能を揃えています」とリウ氏は説明する。
一方、企業向けには「ラマ・クラウド(LlamaCloud)」というクラウド型のサービスも展開している。「これはオープンソース製品を補完する形で提供しており、企業の開発者が文書を構造化し、使えるデータへと変換するのを支援します」とリウ氏は語る。
この2製品は単に用途が違うだけでなく、互いに補い合う関係にあるという。「開発者にとって、エンドツーエンドでAIエージェントを構築・運用できる一連のツールセットを提供しているのです」
こうした戦略の背景には、「AIアプリケーションを実務レベルで運用するには、高品質なデータが不可欠だ」という現場での実感がある。リウ氏は「どんなユースケースでも、最終的に求められるのは高精度のデータです。そこが壁になる」と語る。
従来の文書処理技術との違いについて、リウ氏は次のように続ける。
「例えば、OCR(光学文字認識)や文書理解のソリューションは昔から存在していますが、多くは精度が低く、実用に耐えるようにするには膨大な調整が必要でした。さらに、AIエージェントの活用を前提としたとき、それらの技術は目的に合っていなかったのです」
日本では楽天も導入、チャットツール構築
ラマ・インデックスの革新的なアプローチは、すでに多くのグローバル企業で成果を上げている。中でも、日本企業の導入事例として代表的なのが楽天だ。
「楽天の活用事例は公開していますが、他にも自動車業界やコンサルティング業界の大手企業にも導入されています。多くの企業で、ラマ・インデックスは社内文書の処理やRAGの基盤として、さまざまなAIエージェント構築に使われています」とリウ氏は話す。
楽天では、社内で数十万人が使う横断的なチャットプラットフォームを構築。その中で、ユーザーが独自のナレッジベースを作成できるようにする中核モジュールとしてラマ・インデックスが使われているという。
日本だけでなく、金融、エネルギー、製造業、保険など、世界中のあらゆる業界に導入が進んでいる。例えば、コンサルティング大手のKPMGもその一つだ。
米投資会社カーライル(Carlyle)では、財務デューデリジェンス文書の読み取りと分析を自動で行い、投資判断のための推論や意思決定を支援するAIエージェントを構築している。
また、メキシコの建材大手セメックス(Cemex)では、顧客対応用と社内向けのチャットボットを数十種類導入。既存のソリューションと比べて、精度の面で大きな向上を実現したという。
こうした成果の背景には、急成長するユーザーベースがある。「現在、私たちのプラットフォームには25万人以上のユーザーが登録し、これまでに2億5,000万ページ以上の文書を処理してきました。Fortune 500企業のおよそ300社が、オープンソースまたは商用版のいずれかを利用しています」
事業拡大を支える資金調達も進んでいる。2025年3月にはNorwest Venture Partners主導で1,900万ドルのシリーズAを調達。さらに5月にはデータブリックス・ベンチャーズやKPMGベンチャーズも参加し、追加の資金を確保した。
「調達資金は、開発と営業の両チームの拡充に活用し、あらゆる大企業でAIエージェントが当たり前に使われる世界を実現したいと考えています」とリウ氏は語る。
現在、社員数は約30人。半数が米国に拠点を置き、残りは南米・欧州・カナダなどでリモート勤務している。少数精鋭ながら、グローバル展開を支える体制が整いつつある。
image : LlamaIndex HP CUSTOMER STORIES ページ
目指すのは知的作業の“自動化インフラ”
リウ氏が思い描く未来は、単なるAIツールの進化にとどまらない。文書処理を起点に、ビジネス現場の知的作業そのものを再構築する「土台」をつくること。それが、ラマ・インデックスの目指す姿だ。
「私たちは、あらゆるタイプの文書やデータに対応し、処理から活用までを一気通貫で自動化できるプラットフォームを提供したいと考えています。AIエージェントが本格的に業務を担う時代に向け、その基盤となる機能を構築しています」とリウ氏は語る。
具体的には、いわゆるチャットボットのような単機能の対話AIではなく、推論・意思決定・実行までを担える「業務エージェント」の構築を支援する方向に進化している。
「単に質問に答えるだけのAIではなく、複数のステップを持つ業務フローを処理できるようにしたい。文書を読み取り、必要な情報を抽出し、判断し、次のアクションに移す。そんな一連の知的プロセスをAIが代行できるようにするのが目標です」
現在、AIの導入によって業務効率が2〜10%ほど改善されるケースが多いが、リウ氏は「本当にインパクトのある変化」はこれからだと見ている。
「AIがより多くの判断や作業を担えるようになれば、業務効率は40〜50%以上改善されるでしょう。その鍵を握るのが、ステップを踏んだ知的作業をこなせる『エージェント』なのです」
こうしたビジョンは短期的な改善では終わらない。リウ氏は5年後、10年後を見据え、企業における知的労働そのものの再定義に挑もうとしている。
「私たちは、誰もが簡単にAIエージェントを構築し、それと一緒に働けるプラットフォームを作りたい。エンジニアだけでなく、ビジネス職や非技術者も、自らの課題に合わせてAIを組み立て、業務を進められる。そんな“ユニバーサル・プラットフォーム”を目指しています」
「すべての人がプログラマーになる」とは、コードを書くという意味ではない。誰もが自分の仕事に合わせて、AIという「共働者」を育て、使いこなせる時代を、リウ氏は本気で描いている。
image : LlamaIndex HP
日本市場にも大きな関心、課題はブランド認知
リウ氏は、自社のテクノロジーに自信を持つ一方で、その限界も率直に認めている。
「AIモデルは非常に高性能ですが、現時点では完璧ではありません。文脈を読み取る範囲が制限されていたり、時に誤った判断をすることもある。だからこそ、100%の自動化が前提ではなく、安全に使うための“ガードレール”を設けることが不可欠です」
しかし、リウ氏が最大の課題と位置づけるのは、技術面ではなく「認知の壁」だ。
「スタートアップである私たちにとって最大のハードルは、ブランド認知です。機能面では、むしろ既存の大手プロバイダーよりも優れていると自負していますが、まだそれが十分に伝わっていない」
大企業と話す際に実感するのが、信頼の多くがブランドに依存しているという現実だ。
「セールスフォースやSAP、大手クラウドプロバイダーなどが『安心できる選択肢』とされがちなのは理解できます。ただし、そうした企業のAI機能は、時に非常に基本的なレベルにとどまっていることもある。重要なのは、私たちの技術がどれほど企業の課題解決に貢献できるかを、正しく伝えることだと思っています」
リウ氏は、日本市場にも大きな関心と期待を寄せている。すでに複数の日本企業がラマ・インデックスを活用しており、今後さらにその輪を広げたいと考えている。
「日本企業には、膨大な量のPDFやパワーポイントなどの社内文書がナレッジベースとして蓄積されています。それらを『使える情報』に変えるには、これまで多くの人手と時間が必要でした。私たちは、そうした文書をAIで理解し、調査し、次のアクションに結びつけられるようにしたいのです」
最後に、リウ氏は日本の企業やパートナーに向けて、未来への確かなメッセージを残した。
「AIが、皆さんの社内文書を理解し、活用する存在になる時代は、もう始まっています。私たちは、その未来を実現するための重要なパートナーでありたいと願っています」