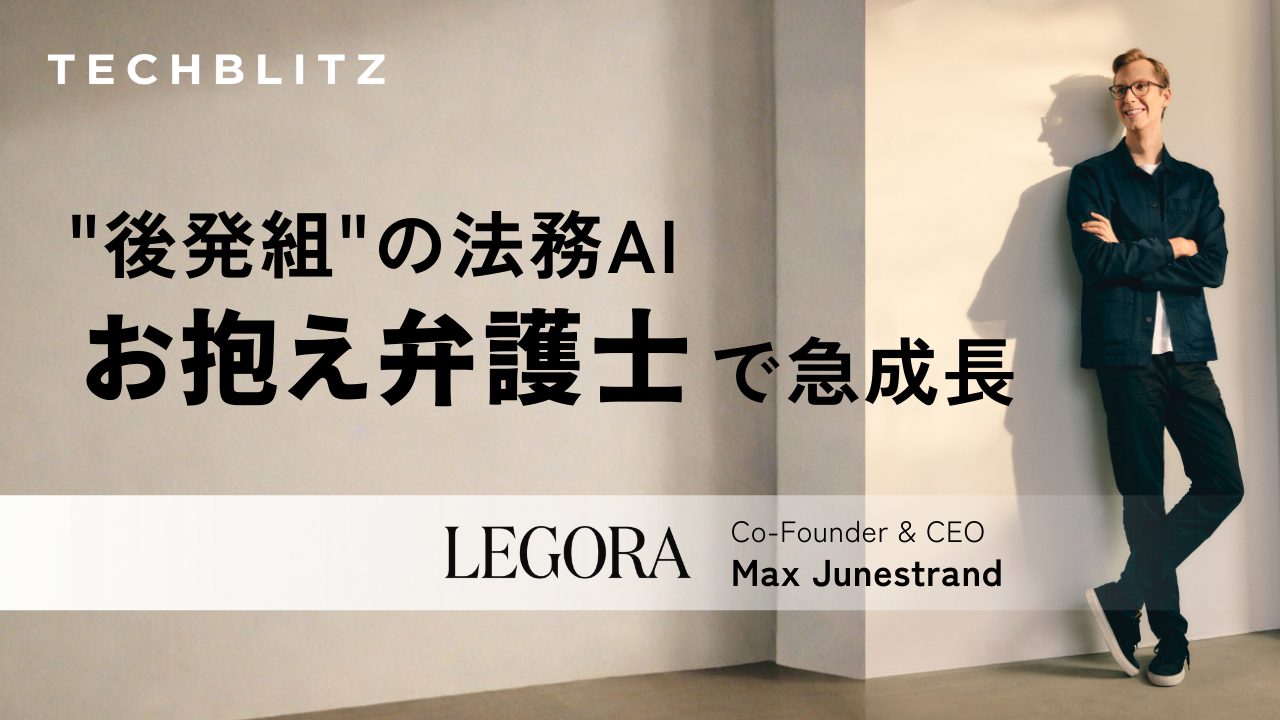目次
・血管の状態を「定量的に」計測することが必要なワケ
・評価→教育→治療→追跡、ワンストップで提供
・約15年間の臨床試験の経験が創業のきっかけ
血管の状態を「定量的に」計測することが必要なワケ
―Cleerlyはどのような課題を解決するスタートアップなのでしょうか。
心臓発作を未然に防ぐ技術を開発しています。心臓発作に由来する死を防ぐことが難しい理由は、それが突然起きること、生活習慣との関連性が必ずしもないことです。当社は、冠動脈CT血管造影画像を独自開発したAIで解析し、血管やプラークを定量化して分析することで、心臓発作の予兆を診断するスタートアップです。
心臓発作の主な原因は、冠動脈疾患(心筋への血液供給が突然絶たれること)ですが、これは突然起きます。発作が起きる前に胸痛や息切れといった前兆を起こしているケースは稀です。だからこそ、冠動脈疾患を防ぐには定期的に心臓を検査し、さらにこの検査・解析の精度を高める必要があります。従来、このプロセスには数時間かかっていましたが、当社はこれをわずか数分以内にまで短縮しています。
ちなみに、生活習慣と冠動脈疾患には明確な因果関係がありません。極端な話ですが、たばこを30年間吸い続け、コレステロール値が高い人が心臓発作を起こすとは限りませんが、世界ランキング2位のトライアスロン選手がマラソン中に発作を起こしたケースもあります。
冠動脈疾患の基本的なメカニズムは、動脈にプラーク(コレステロールやカルシウムのかたまり)が形成されることだということは分かっています。ただ、プラークが蓄積されるのは、生活習慣や遺伝、ストレス、公害など様々な原因が考えられるのです。
こうなると、単に「食生活に気を配りましょう」「運動しましょう」と呼びかけるだけでは、心臓発作を防げないことが分かります。突然死を防ぐためには、冠動脈など心臓の血管の状態を「定量的に、継続的に」測定するしかないのです。
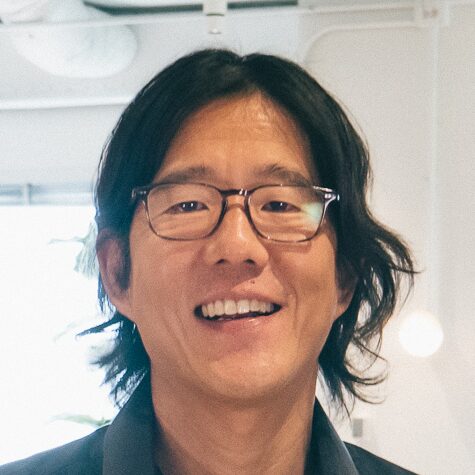
評価→教育→治療→追跡、ワンストップで提供
―具体的にどのような測定を実践しているのですか。
心血管の評価から教育、治療、追跡までワンストップで医療機関に提供しています。評価に関しては冠状動脈CT血管造影で撮影した心血管画像をクラウドにアップロードし、機械学習を用いてこれを分析します。その上で、解析結果を患者が理解できる形にします。さらに、解析結果を基にスタチン投与など、有効な治療法も提案します。薬が効いているかなど、心血管の状態を定量的に追跡できるのです。
とりわけ特徴的な技術は、CT画像の解析精度を飛躍的に向上させた点です。従来の検査方法ではプラークの形態までははっきり見えませんでしたが、当社のAIはこれを鮮明に切り取ることに成功しました。
当社がターゲットとする市場は非常に大きいものです。潜在的に心臓発作のリスクを抱えている患者の市場は米国だけで約1億8,000万人で、実際に胸痛や息切れの症状がある人は年間1,500〜2,000万人います。私たちのビジネスモデルは、医療機関からの保険請求がメインなので、保険会社にとってもCleelyを活用することで、医療コストを削減することが可能ですし、医療機関は患者の心臓の状態に関する包括的なデータを得ることで、より緻密な治療計画を立てることができます。何より患者も、これまでは定量的な診断が難しかった心血管の状態を確認できるのですから、保険会社・医療機関・患者の3者にとって優れたプラットフォームだと言えます。
当社のソフトウエアはすでにFDA(米食品医薬品局)の許認可も取得しているなど、信頼性も高いのです。
―Cleerlyを利用する医療機関からはどのような反応があるのですか?
反応の声は以下2つに集約されます。「早期に患者を見つけることができた」というものと、「意味のない薬を投与せずに済んだ」というものです。前者に関して、心臓発作は早期診断と状態の追跡で、一定数は未然に防ぐことができます。後者に関しては、従来の手法は解析結果にばらつきが出ることも多く、患者は誤った結果に基づいた薬を飲んでいることも多いため、こうした声をいただきました。
このような評価から分かるように、当社は過去5年間で毎年対前年比100%以上の成長を遂げているなど、市場からの評価も高いのです。

image : Cleerly
約15年間の臨床試験の経験が創業のきっかけ
―Minさんは2019年にCleerlyを創業しました。創業のきっかけは?
私はテンプル大学医学部を卒業し、その後はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)やDalio Instituteなどで心臓病理学の研究に従事しました。当社を創業した直接のきっかけは、2005年にCT技術の臨床利用が可能になったことです。それ以降の約15年間、CT技術を用いて心血管や心臓発作の大規模臨床試験に取り組みました。その結果、プラークの種類と形態が患者の転帰(疾患の治療における症状の経過や結果)に直接の因果関係があることと、スタチン治療が心疾患リスクを大幅に減少させることを立証しました。
さらに、5人の循環器専門医と共に、CTスキャンを用いた「画像解析プログラム」を7年間実施した結果、1件の心臓発作も起きなかったことを突き詰めたのです。一方で、従来の画像解析は1人に対して何時間もかかっていたことから、大規模展開が不可能だという課題も分かっていました。そこで2019年にCleerlyを創業し、AI技術を活用した画像解析の短縮化を試みたのです。
―日本市場への進出は考えていますか?
日本市場は米国に次いで、冠状動脈CT血管造影の実施件数が世界第2位であり、Cleerlyに対する潜在的なニーズが大きい国だと思います。さらに、日本の医療保険制度は欧州と比較して新技術に対する償還条件が良いため、展開もしやすいのではないでしょうか。また、社会の高齢化が著しく、検査に対するニーズが高いことも特徴的です。
ただ、当社は向こう数年間はアメリカでの展開に集中する予定です。時間はかかっても良いので、日本市場を知り尽くしたパートナーが現れることを期待しています。
―どのような分野において、日本企業との協業を望んでいますか。
主にヘルスケア分野におけるOEM企業でしょうか。日本には医療を専門とする優れたOEMメーカーがたくさんあると聞いています。規制面の突破も含め、そういった方々と話をしてみたいですね。
日本企業とのパートナーシップを考えた時、優先したいのは代理店か合弁会社の設立でしょうか。私たちは技術に関しては自前で届けられますし、今のところ資金も潤沢にあります。日本市場を深耕できるパートナーが最適でしょうね。