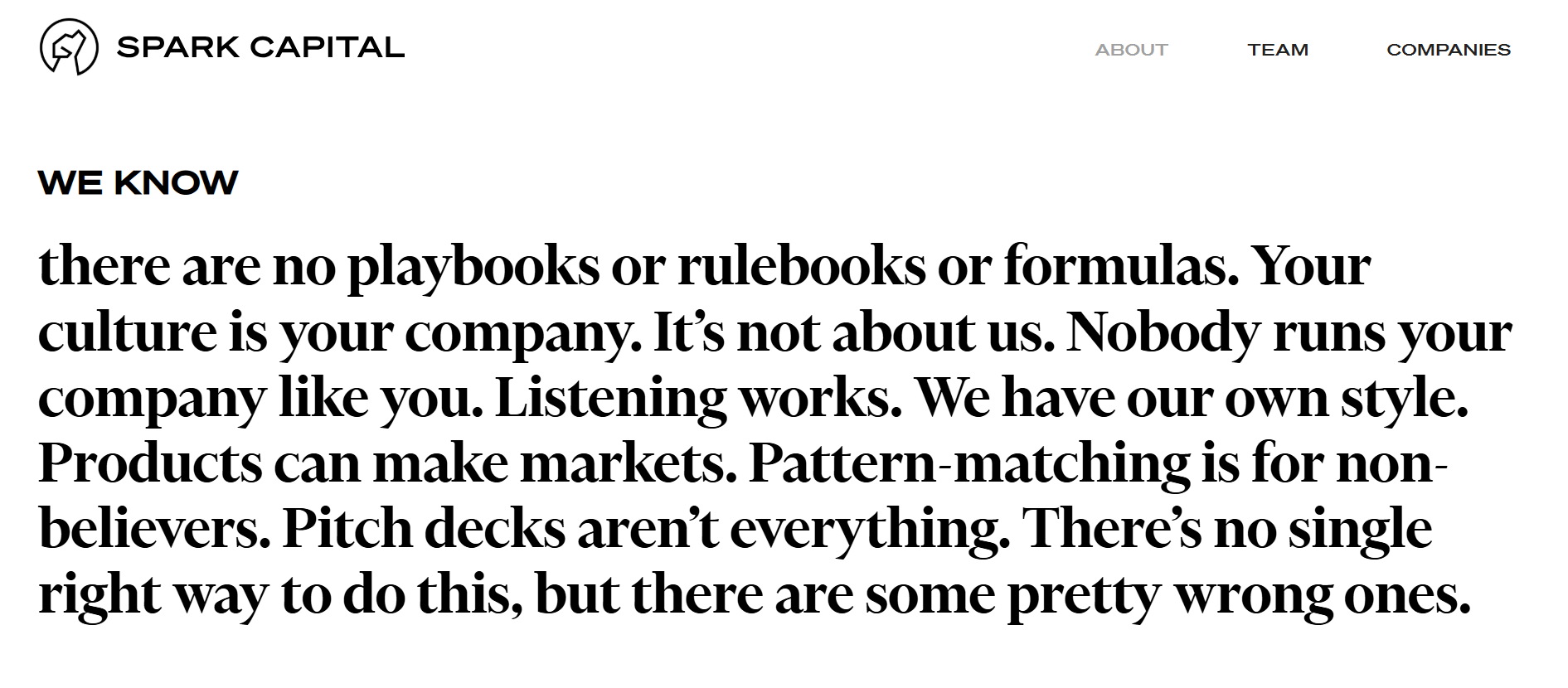目次
・投資哲学は「その技術は世界を変えるか?」
・スタートアップ投資と株式投資の大きな違い
・アンソロピックへの投資を決めたロジック
・起業家に寄り添う、小さくて強いVC
・今の日本に圧倒的に足りないものとは?
投資哲学は「その技術は世界を変えるか?」
―スパークキャピタルは、どのような投資戦略を掲げているのでしょうか?
私達の信念は一貫しています。「5年後の世界を根本から変えるテクノロジー」を見つけ出し、それを生み出す企業群にいち早く投資することです。
例えば2008年、私たちがツイッターに投資した頃、ソーシャルネットワークサービス(SNS)が急速に注目を集め始めていました。こうした新興分野では、多くのスタートアップが次々と登場し、どの企業がリーダーになるかは当初ほとんど見分けがつきません。
実際、私たちはツイッターやタンブラーといった後の成功企業に投資する一方で、今では名前も知られていないSNSにも同時に出資していました。重要なのは、「どの技術が世界を変えるのか」を見極めること、そして「その技術がどう社会に広がるのか」を読み解くこと。そして、その分野全体をカバーするように、複数の企業に分散して投資していくのです。

この戦略を「ずいぶん大ざっぱだ」と感じる人もいるかもしれません。でも実は、これはベンチャーキャピタルの投資戦略における王道中の王道。世界の産業構造や人々の暮らしを根底から変えてしまうようなテクノロジーは、必ず周期的に現れます。その波が来たとき、リスクを恐れずに最初の一歩を踏み出せるかどうかが勝負なのです。
もちろん、全ての投資が成功するわけではありません。でも、イノベーションのインパクトが大きければ大きいほど、その中の数社が突出して成功し、結果として大きなリターンをもたらしてくれます。
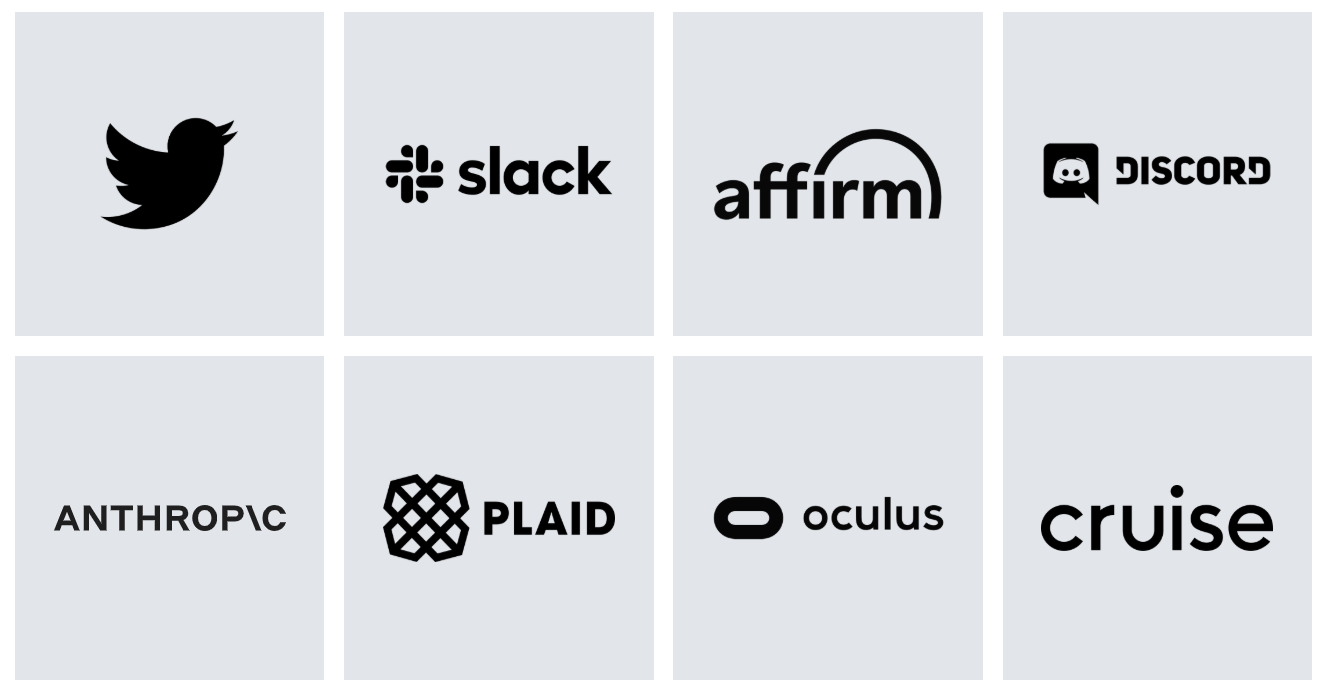
image : Spark Capital HP COMPANIESより
スタートアップ投資と株式投資の大きな違い
―「未来を信じて投資する」ことが重要だということでしょうか。今のように株式市場が目まぐるしく変動し、地政学的な不安も高まる時代においては、特に勇気が必要な決断に思えます。
たしかにそう感じるかもしれませんが、例えば生成AIの分野を見れば分かる通り、世界を変える可能性を持った技術は今この瞬間にも生まれています。そして、そこに挑む起業家の多くは才能に溢れ、短期間で急成長する企業も数多く出てきています。
私たちVCが出資するアーリーステージでは、投資期間は一般的に2年半から3年ほど。これだけの時間があれば、テクノロジーの本質や大きな潮流を見極めることは十分に可能です。
むしろ重要なのは、「みんなが不安を感じている時こそ、恐れずに動くこと」。VCの仕事は株式投資とは違い、短期的な相場の浮き沈みに振り回されるものではありません。世の中がどう変わろうとしているのか、その変化の兆しを掴むためには、マーケットのノイズを遮断し、未来に向けた静かな確信を持つことが必要です。
そして、VCには「時間を味方につけられる」という強みがあります。つまり、起業家と密に対話しながら、企業の成長フェーズに応じて、資金の投入タイミングや人材採用、研究開発への投資などを柔軟に調整することができる。仮に一度つまずいても、軌道修正する時間があるのです。
対照的に、株式投資では「いつ買うか・いつ売るか」という時間の制約に縛られます。その点、VCは長期的な視点でスタートアップと伴走し、変化を前提としたサポートができる。これがVCという仕事の大きな魅力であり、可能性なのです。

「みんなが不安を感じている時こそ、恐れずに動くことが重要」と語るポリティ氏(TECHBLITZ編集部撮影)
アンソロピックへの投資を決めたロジック
―読者の多くもきっと関心を寄せているのが、やはり生成AIの潮流をいつ、どのように見極めたのか、という点でしょう。スパークキャピタルは2023年5月、シリーズCラウンドでアンソロピックに出資していますが、その背景にはどのような判断があったのでしょうか?
アンソロピックへの投資には、私たちがツイッターに出資した時と同じロジックがあります。先ほど申し上げた通り、「世界を変えるテクノロジー」に対しては、早期にリスクを取って飛び込む――それが私たちの信条です。そして、生成AIはまさにその典型でした。
私たちはアンソロピックに最初に出資したVCの1社です。その時点で私たちが重視していたのは、「生成AIという市場が、今後どのように進化していくのか」を多角的に読み解くことでした。
「生成AI市場は、たった1社が覇権を握る構造になるのか?」「それとも複数プレイヤーがしのぎを削る競争になるのか?」「グローバル展開はどんな構造になるのか?」「技術的・倫理的な課題や、国家安全保障への影響は?」──。こんな問いを自らに投げかけていました。
こうした問いに対して、私たちはチーム全体で毎日議論を重ねてきました。企業のビジネスモデルやチーム構成を見るだけでなく、「生成AIというテクノロジーと、それがつくる新しい産業構造」をセットで深く分析したのです。
その結果、私たちが導き出した投資基準はこうでした。
「生成AIのコア領域に長年携わってきた人や組織に投資する」こと。
生成AIは突如として登場したように見えるかもしれませんが、実際には長年にわたり研究が積み重ねられてきた分野です。だからこそ、直近でこの分野に参入しただけの企業がリーダーになるのは極めて難しい。物理学や統計学の博士号を持ち、自然言語処理やアルゴリズムの研究を行い、実際に企業で大規模言語モデル(LLM)の開発を担ってきた人物でなければ、本質的なイノベーションを起こすことはできない――それが私たちの結論でした。
アンソロピックは、まさにその要件を満たしていました。OpenAIに在籍していた研究者4人が創業メンバーで、彼らはすでに多数の論文を発表しており、LLM領域では一線の専門家です。OpenAIを離れたのは、主に倫理的なスタンスの違いであって、技術力においては互角。事実、両社は長らく“抜きつ抜かれつ”の関係にありました。
つまり、アンソロピックは「成功のシナリオが最初から見えていた」スタートアップだったのです。しかも当時、OpenAIはすでに評価額が非常に高騰しており、そこに対抗できる存在に早期に賭ける意義も明確でした。
また、私たちはアンソロピックだけでなく、アデプトAI(Adept AI)にも出資しています。人間のコンピューター操作を代替する生成AIを開発していたこの企業は、のちにアマゾンに買収されました。
こうした展開も、ある程度予測していたことです。なぜなら、GAFAMのようなテックジャイアントは、自社で独自のLLMを持ちたいと必ず考える。しかし初期フェーズでモデルを構築し、学習データを蓄積してきたスタートアップには、どうしても追いつけない部分がある。だからこそ、彼らはいずれスタートアップと提携・買収に動くだろうという確信があったのです。

テクノロジーの潮流を見極める思考法について語るポリティ氏(TECHBLITZ編集部撮影)
起業家に寄り添う、小さくて強いVC
―生成AIの技術革新は日々加速しています。将来的には、どのような社会が待っているとお考えですか?
AGI(汎用人工知能)の登場によって、人間の仕事がすべて奪われてしまうのではないか――そんな懸念もたびたび耳にします。確かに、新しい技術が登場した時、政府の規制や社会制度の整備が後手に回ることは歴史的に見ても避けられません。
それでも、私は楽観的に未来を見ています。特に先進国では、急速な少子高齢化により、工場や病院といった社会インフラの担い手が不足しています。こうした課題を解決し、人々の生活水準を維持するには、AIやロボティクスの活用が不可欠です。
今後は、誰もが「プロジェクトマネージャー」のような立場になるかもしれません。プログラムはAIが書いてくれ、アプリもAIが作ってくれる時代。つまり、モノ(テクノロジー)が人間のために働いてくれる社会が、すぐそこまで来ているのです。
―他のVCと比較した時、スパークキャピタルにはどのような強みがあるのでしょうか?
私たちは、大規模なVCに比べて、組織としても投資先の数としても小規模です。だからこそ、アジャイルに、そして密に、起業家と並走することができるのです。
単に資金を出すだけではありません。採用戦略、チームビルディング、マーケティング支援まで――外部のプロフェッショナルだからこそ提供できる価値が私たちにはあります。創業初期の企業にとっては、こうしたサポートの一つ一つが、成功の確率を高める大きな後押しになると信じています。
そして何よりも、私は起業家という存在に深い敬意を持っています。
彼らは本当に才能があり、そして本気で世界を変えようとしています。スパークキャピタルの役割は、そんな起業家たちが本来の力を最大限に発揮できるように環境を整え、背中を押すこと。ただ、それだけなんです。
image : Spark Capital HP
今の日本に圧倒的に足りないものとは?
―日本市場について、どのような印象をお持ちですか? ポリティさんは30年前、パナソニック本社で勤務されていたご経験もありますよね。
正直なところ、日本のスタートアップシーンは物足りません。名前を挙げられるスタートアップはSakana AIくらいです。日本には、大企業も、優れた大学や研究機関も揃っています。政府も様々な支援策を講じています。それでも、有力なVCやスタートアップが育ちにくい現状は、非常に残念です。
日本が得意としてきたのは、既存技術の改良や洗練です。確かに、家電や自動車など、消費者向け製品で世界を席巻した時代がありました。ただ、個人的な意見としては、日本はゼロからまったく新しいものを創ることが苦手で、「破壊的イノベーション」を起こすには、まだ課題が多いと感じます。
―では、どうすれば日本のスタートアップエコシステムは活性化するのでしょうか?
もちろん、30年前と比べれば日本は大きく変わりました。人口減少が進み、労働力不足が深刻化するなか、多くの外国人も流入しています。これは大きな変化であり、チャンスでもあります。ただ、それにしても日本の人手不足は本当に深刻そうだと感じます。パナソニックの当時の上司も、70歳近くになってもまだ働いているほどです。
私の目から見ても、日本は「起業家大国」になれるポテンシャルを十分に持っています。起業家をたくさん輩出するには、特に若い力の存在が重要ですが、人材も、研究インフラも揃っている。それでも何かが足りない――そう考えた時、真っ先に浮かぶのが「リスクマネーの不足」です。今の10倍、いや100倍は必要です。
―文化的な側面も関係しているのでしょうか?
そうですね。「失敗を恐れる文化」も大きな壁です。日本は失業率が低く、社会全体としては安定しています。でもそれは裏を返せば、リスクをとって挑戦する理由が乏しいということでもある。
本当に成功する起業家というのは、「これを実現しなければ、生きていけない」と感じるような、抑えきれない衝動を持っています。どんなに危険でも、その道を選ばずにはいられない。日本のように安定した社会では、そうした「やむにやまれぬ情熱」が生まれにくいのかもしれません。
私は日本という国が大好きです。パナソニック時代を振り返ると、「モーレツサラリーマン」でしたね。毎日残業して、毎晩のように飲みに行って(笑)。でも、それもすべて良い思い出です。
今、私は投資家という立場になりました。だからこそ、日本に対する期待は大きいのです。これから世界を変えるのは、かつてのトヨタやソニーのように、スタートアップから生まれてくるはずです。偉大な起業家の登場を、心から楽しみにしています。米国から、ずっと応援していますよ。